ばあ
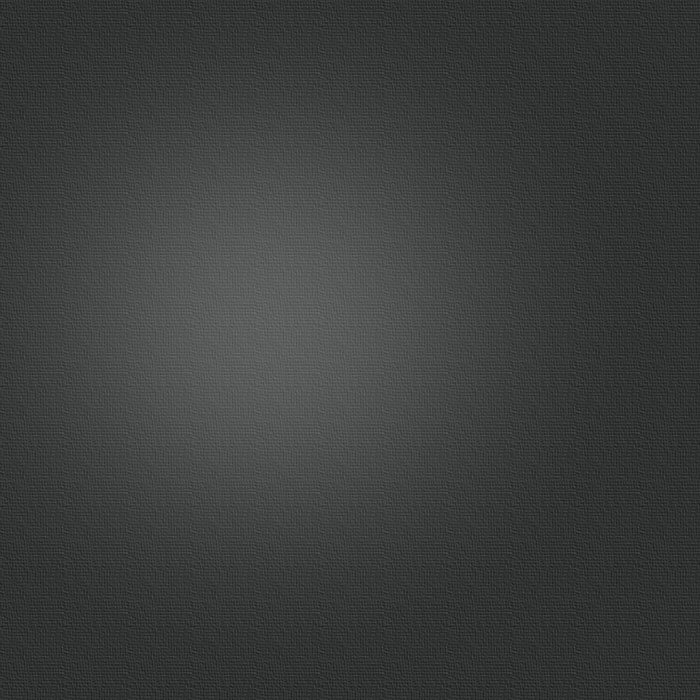
ばあが入ってしまった。
北枕。寝床の位置を変えたのがいけなかった。左脇の、東へ向いた窓から入ってしまった。一番眠りの深い時分のことだと思う。二階の部屋はまだ暗い。
勢い余ったのだろうか、入ってくるなり猛烈な速さで転がる丸太のよう、クルクルクルッ、クルクルクルッ、と異常な往復回転運動をする。目が追いつかない。何をしたいのか分からないが、狂ったよう一人勝手に床で転がるのである。
そこはニイカが死んだとき一晩安置したところ、部屋の北側の出入り口にあたる場所だった。その所為もあったと思う。並ならぬ速さで転がるばあが回転を反転させる一瞬の静止、その時目にするばあの姿はニイカの骸に見えている。白と茶色のシェットランド・シープドックと同じ長い毛で覆われて、大きさも丁度ニイカほどなのだ。
ばあが入り込んでしまう原因。それは犬の所為と察しがついている。今飼っている犬、それを私は可愛がり過ぎている。その鐘愛がばあを呼び込むのだ。そしてばあのもたらす厄もその鐘愛へと作用する。しかしその作用の結果、具体的にどういう事が起こるのかは分からない。分からないのだが、こうしてばあが入ってしまった以上、何かされることは間違いない。今の犬を連れていってしまうかもしれない。もしそうなら、私にとってそれが一番辛いことだ。
これは何か手を打たねばならない。とても敵う相手でないことは分かっている。だが何かするなら今だ。今、目の前で夢中に転がるばあになら、私も何か手を下すことが出来そうだった。
コロコロコロとこちらへ転がってきて、次に反転する頃合いを見計らう。そしてその時、手を添えて左方向へ向きを変えてやる。
回転運動を利用して西側の壁へ追いやってみたのだ。昨日まではそこに寝床を設えていたのだが、今は何も置かれていない。床と壁の90度。そこへ追い込む。
ばあはそこで突き当たる。
そこでばあは空回りしている。
その先どうしたらよいのかは考えていなかった。ともかく思い付きでそこいらにあった毛布やら夏掛けやらを手当たり次第被せていった。そしてもぞもぞと動く布団の山になったその上から、上半身に体重をかけ両手でぎゅうっと圧しているのだ。ドクッ、ドクッ、と布団越に押し戻されるばあの呼吸、心拍。生き物を圧殺するときの反動が伝わってくる。しかしばあはこれくらい何でもないはずだ。むしろ中途半端なこの撃退行為が、かえって事を悪く運ぶに違いない。場当たり的なことをしてしまい、その先が続かない。
怖くなって自分の寝床に潜り込んだ。子供みたいに頭から布団を被って、ただ念じていた。
「どうかお帰り下さい、お帰り下さい...」
呪文のように唱えるのだった。
気配がする。ばあがもぞもぞ這い出る気配がする。そして布団を被った私の足の方へとばあが移動してくる様子が窺える。
「お帰り下さい...お帰り下さい...」
このまま諦めて帰ってくれることを願って呟く。
一瞬静かになった後だった。かしっ、と足首を掴まれる。下の方、掛け布団の隙間からばあの手が入ってきて、私の両足首を掴んだのだ。冷たい手でぎゅうっと掴まれる。
このまま引きづり出されるのだろうか。恐怖感に見舞われるが、私は敢えて抵抗しなかった。ばあになされるままでいた。
「もう分かったでしょう、私は何もしません。だから、お帰り下さい...」
ばあが仕返ししないはずないと分かっていた。しかし私としては打つ手がない。せめて無抵抗で、こちらに敵意がないことを分かってもらうしかないのだった。
するとすっと冷たい手が離れる。
また静かになった。
この間は何だろう。溜、ではないだろうか。次の行動へ移行する前の、溜。
ドサッ。
腹の上にドサッと乗った。
見ないでも分かる。床からそのまま跳んで上に乗ったのだ。長く伸びた爪を生やした四脚で鷲掴みするよう、羽毛掛け布団の上から私を踏み台にしている。重く、苦しい。さすがにじっとしていられない。身を捩って抵抗するが、ばあは踏ん張っている。鋭い爪が羽毛布団に減り込んで、直接私の身体を掴もうとしている。痛い。尖った爪が、痛い。
このままどうなってしまうのか。恐怖のどん底へと落ちていった。
落ちていった頃、ふっ、と急に身体が楽になる。
ばあが退いたのだろうか。
ばあは去ったのだろうか。
頃合いを見計らい布団から顔を出す。そして掛け布団を剥いで上半身だけ起こしてみる。
静かだった。ばあの気配がしない。
目が慣れてきて寝床の周りに落ちているものが見えてきた。糞。犬の糞がそこいら中ごろごろ転がっている。それと、糞に混じって履き物が、鼻緒の付いた履き物が揃っていくつも置かれている。どこから運ばれてきたのか、それはカナエサンの履いていた下駄や草履なのである。彼女の物は全部処分したつもりでいたのに、履き物だけは家のどこかにしまってあったのかもしれない。だが、それがどうしてここにあるのか。
きょとんとニイカが私を見ている。
死んだニイカがそこにいて、よくそうしたように、真ん丸の目をこちらへ向けてきょとんと私を見つめている。
そうか、ニイカが咥えて持ってきたんだな.....
カナエサンが出ていってから、入れ替わりにやってきたこの犬(キツミ=ニイカ)を大切に育てていた。あんなに可愛がっていたのに、結局ニイカ(=キツミ)はカナエサンが好きでたまらない。きっと忘れられないのだと思う。そう思うと不憫に感じ、同時に私が寂しくなってくる。私の愛情だけでは足りないということが辛く、寂しいのである。
こみ上げてくる辛さで口の中が一杯になった。
もどすために流しへ走る。
北側にある部屋の出入り口から廊下が続き、左手にトイレ、そして台所と呼ぶにはあまりに見窄らしいが、流しとガスコンロの置かれた場所がある。その流しで吐いていた。
口の中を一杯にしていたのはちいさなつぶつぶだった。澱粉質の周りに胃液が付着して凝固した粒ではないだろうか。乳白色したカエルの卵のような、ちいさなつぶつぶがどっさり。気持ち悪くて吐きもどすのだが、次から次と湧いてくる。止まらない。こんなものが湧いてくるのもばあの所為なのかもしれない。これがばあの厄なのだろうか。他になにか異変はないか、流しへ向かい嘔吐を繰り返す合間、気になって左方の部屋の方を見遣る。するとまだニイカがきょとんとこちらを見ている。円らな瞳でじっと、嘔吐する私を見つめている。
そんな時だった。とんとんとん、と階段を上がってくる音がする。
こんな夜更けにカナエサンが帰ってきたのである。
ニイカが尻尾を振って出迎える。そしてカナエサンとニイカが暗い部屋の扉の辺りに佇んでいる。私の様子をそこから黙って見つめている。
あの日突然いなくなり、もう戻りません、二度と会うこともありません、と書き置きに記してあったのに、どうしてこんな時分突然帰ってきたのだろうか。
何か言うべきだ。私から何か、言うべき事を言わなくてはならない。そう思うのだが、口の中に溜まったつぶつぶの所為で上手く発話できない。何か言おうと思っても苦しくて言葉にならない。それでも無理に言葉を発してみた。どろどろどろっと、口から白い粒状物を垂らしながら発話する。それは自分でも驚くほど、ゆっくりと低い、おぞましい声になっていた。
「ナンデ カエッテ キタ...」
黙ったままカナエサンはこちらへ来る。そして流しの正面の窓、西に面した窓枠にふてぶてしい態度で寄りかかっている。
「ヒドスギヤ シナイカ...」
ごぼごぼごぼっと吐きながら、同時に私は右手を差し上げ、人差し指で彼女を指しながら言っている。そんなつもりもないのに、これ以上ないほど怨霊の籠もった声になって。
私から目を反らした彼女は窓の外を見ている。横顔が見える。ぼんやり薄暗がりに彼女の頬が見える。痘痕の酷い頬だ。
何喰わぬ様子を見せていても、どうも内心怯えているらしい。得体の知れない粒状物を口から垂らし、おどろおどろしい声で語りかけてくる私を怖がるのは当然だ。おそらく無理に平常を装い私を無視している。私は私で、自分がばあのような超常的存在、他者へ厄を与える存在になっていることを楽しみはじめていた。そこまで恨んでいるわけでもないのだが、自分の言動に怨霊染みた力が備わっているのなら、せめて、味わった苦痛の仕返しに利用してやろう、そう思っているのである。ゆっくりと指さすその行為だけでも、今はかなり不気味なはずだ。
やりすぎたようだった。彼女は怯えて、それで狂ってきたようなのだ。
黙ったまま目が異常に吊り上がってしまい、ソバカスのあるアメリカ製のビニール人形が凶暴化したような不気味な顔になってひきつっている。寄りかかっていた窓枠から外の方へ身を傾け、もう上半身から落ちかかっている。やめようと思いつつ、つい指さして、更に恨み言を漏らすと、どすんとそのまま外へ落ちてしまった。一階の玄関の上の庇に落ちて、身体をくの字に曲げて、もがき苦しんでいる。
2011年1月12日
夜中、たぶんキツミがどさっと私の上に乗ったのだと思う。
うなされるほどの怖い夢だった。
夢の中でキツミとニイカを混同している。
キツミをもらってきたのはカナエサンの出て行った翌日。
キツミはカナエサンを知らない。
2011年1月12日

