会津本郷雪中食堂
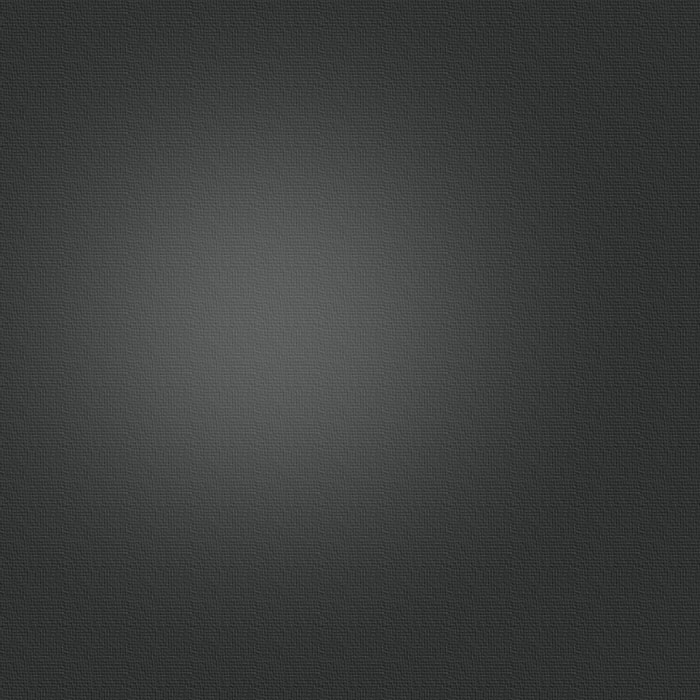
盤根錯節に遭う。
鬼怒川、川治を越えるともう会津の豪雪地帯に入っていた。四方八方真っ白。広大な雪原を切り分けるよう真っ直ぐ県道が延びている。幌型、寒冷地仕様の軽四輪駆動車で山形へ向かう途中だった。食事休憩をとることにしたのだ。
会津本郷辺りかもしれない。車を降りて見渡すそこは、他と区別することのできない、やはりただの雪原でしかない所。食堂どころか建物も何もない、ただただ真っ白な雪の広野。それでも僅かに雪の盛り上がった場所がある。そこが入り口とどうして知ったか、そこから潜っていくのである。落ちるようではない。掻き分け、身体を捩り、上と下が分からなくなって一瞬呼吸も止まる苦しい体勢で通過してゆく。それは身に覚えのある通路だ。いや通路と呼べるだろうか。構造化されていない窮屈な通過廊、穴を掘って進むのではなく、あらかじめそこを通過させることを前提とした非建築的通路。雪に埋まってそうなってるのか、それともそういう入り口なのかは分からない。ともかく一旦頭から、逆さになって潜ったのだ。真下へ向かい潜る。そんなにしない内、今度は真横へ進む。その「くの字」に身体を曲げる時、多少苦しい思いをする。そうして地面と平行する、と思われる、地下トンネルらしき、やはり非建築的、言い換えれば有機物、器官のような管、目に見えず、触れる感触もない窮屈な管のような雪の洞をもがいて這って通過して、ようやく店内へと落ちる、そういう入り口から食堂へと足を踏み入れたのだった。
さてその食堂、こんな辺鄙な所にあって、しかも苦痛を伴いようやく至る入り口の構造からして、繁盛している気配もない。寂れた温泉街にある「ラーメン」の暖簾を出した食堂、「営業中」の吊し書きでようやく「つぶれてないんだ」と分かる見窄らしいラーメン屋のようであり、そうだとするとここは川治の温泉街か、川治が町ごと雪に埋もれたかと思う始末。いや、やはりここは会津本郷。地面の下に店がある、雪に埋もれて店がある、どちらもまともに考えればありそうにないが、温泉街でないことは確か。それよりやはり、逆さになって、苦痛を伴いようやく至る入り口の構造、客商売としてそもそも成り立つのが不思議と思っていると先客がいる。後ろ姿でもすぐ分かる。カオリサンだった。カオリサンが一人、シジミチャーハンを食べている。私より先に着いたのか、と納得している。そう、「私より先に着いた」と解釈しなければ、どうしてここにカオリサンがいるのか説明できないからだろうが、どうやってこんな場所まで来れたのか、後から説明するのは困難なはず。それより彼女の注文品、スープ付きシジミチャーハンのそのシジミ、殻付きで妙に大きい。アサリではないか、と修正するのは覚めた後、アサリチャーハンなら意味が通ると、夢から覚めて思うのだった。ただみんみんのアサリチャーハンは殻付きではないのだが。
荻窪北口の、現在は駅ビルと繋がったタウンセブン。町、七つ?「七」はその商店の数なのかどうか名称の経緯を知らないが、そこは昔「マーケット」と呼ばれた迷路状の市場だった。中島飛行機東京製作所を狙う米軍の爆撃。その煽りで北口は焼け野原になったらしい。戦後その焼け跡に闇市ができる。高度経済成長期に入ってもマーケットは闇市の面影を引きずっていたことになる。幼児期の記憶では、その一帯はまるで迷路だった。バラック、トタン屋根、裸電球、どぶ板を渡した狭い通路、昼でも暗く、鮮魚店から滴る水の所為で、いつも湿っていた北口マーケット。70年代終わりには現在のビルへと代わっていたはずだ。そんな荻窪北口マーケットを彷彿させる現在の吉祥寺は通称ハモニカ横町。駅前の通りから、どこをどう通ったか、未だに覚えぬ迷路を進む、ハモニカ横町どこかの奥にみんみんはある。大振りの餃子が名物だ。
大阪万博の頃からだろうか。サッポロラーメンなるものが普及する。それまで味噌ラーメンなどなかったのだ。みんみんは、そうした「初期サッポロラーメン」の店舗として現在でも営業を続ける、もはや老舗だ。狭い店内、僅かにテーブル席があるものの、大体は窮屈なカウンター席になる。昼時など混雑するのである。品書にはその、名物の餃子、餃子定食、塩、醤油、味噌のラーメン、そしてアサリチャーハン。
カナエサンが度々アサリチャーハンを注文したのである。私も一度は食べてみようと頭では考えるのだが、いざ席に着けば味噌ラーメンと餃子を注文している。一度も食べたことはない。
二人で外食した最後の記憶、それは吉祥寺みんみんなのである。その時も彼女はアサリチャーハンを注文したのだ。私はやはり味噌ラーメンと餃子だった。
カオリサンの小さな後頭部越しに平皿に盛られたチャーハンが見える。その皿の左隅には開いた二枚貝が沢山添えられている。大きさからすればアサリのはずだが、シジミだと思っている、シジミチャーハン。
ああ、シジミチャーハンにしたのか、なるほど、とカオリサンに感心している。私もそれにしようと考えていたのである。初めて立ち寄る店と思っていたが、何度か来ているような気にもなる。
シジミがいいから、と友人に勧められたのがきっかけだと言う。姉が私にもシジミ汁を出してくれたのだ。いや先日ご馳走になったのは、退院したての姉に代わって義理の兄が作ってくれたのだっけ。
「シジミを水に浸したまま火に掛けて、そのまんま煮て赤味噌足すだけだよ。」と義理の兄が作り方を教えてくれた。突然連れ合いを失う恐怖を兄も垣間見たのである。慣れない家事に勤しむことが、せめてもの慰みとなったのではないか。
厄介な手術は無事成功した。だが転移、再発の不安と共に暮らさねばならない姉。周りから色々病気にいい食べ物を勧められるそうだ。「そういうの、なんかやだよね。」と私にこぼす。美味しいから食べる、食べたい、それでいいじゃないか、と三人で話す。
ともかく、シジミは姉の病に効くらしい。
カオリサンと同じものを注文するのは止めようと思う。かと云っていつも通り味噌ラーメンを注文するのも芸がない。
「醤油ラーメン」と厨房の中で声を出していた。
厨房の中でである。
実際にはカウンターから半身を乗り出し注文したのかもしれない。だが意識としては、私は厨房の中にその時いたのだ。
店の親父は柱に寄りかかっている。貧弱な木柱、一本柱である。改築に改築を重ねたのか、民家だった壁をぶち抜き、構造上外す訳にはいかずそのまま残された木の柱が厨房内の動線に介入している。調理台から離れたその柱に、腕組みをして左足をくの字に曲げて、白い長靴の底を柱側面に当て、無愛想に寄りかかっているのである。被っている調理帽は頭頂の平らになっている型。白の前掛け、上着はやはり白い調理服。一方左手の流し台では、親父よりは少し若い男が洗い物に専念している。使用人と云うより、もうずっと古くから共に店を切り盛りしてきた仲と見受けられる。そして私の注文を直接受けたのは、右手にいる三角巾を被ったおばさんだ。白い前掛けをしている。長く連れ添った親父の女房なのだと思う。厨房内に三人いる。家族同然の男一人を交え、夫婦でこの食堂を営んでいるのである。
「味噌でいーよ。」
寄りかかったまま親父がぼそっと言う。太太しい態度だった。客の注文を反故にする、そういう店の経験がなく、初めは何を言ったか分からないほどだった。しかし確かにそう言って、柱に寄りかかったままその体勢を崩していない。
怒る権利がある、と転轍機が切り替わったらしい。度が過ぎて、私は与太者へと憑依する。
凄んだ私の口を衝いて出るのは、巻き舌が入るほど誇張された脅し文句。キャクノチュウモンヲナンダトオモッテルンダ。内容はその程度のことなのだが、どんなに言っても治まらない。どう仕返しするか、もっと直接的な行為に及ばねばならないだろうか思案する羽目になる。
思案する内眠ったようだ。
微睡みからゆっくり帰ってくる。
目の前が白い。右肩を下にして、雪の平原を横向きに、くの字になって寝てたのだ。頬が雪に触れている。だが冷たさは感じていない。戻ってきたのだろうと、そのままぼんやり思っている。
目が慣れてくると、溶けかかった雪の水溜まりがある、そのすぐ縁に寝てると気付く。寝たまま手の届きそうな所、そこに何か萎びたものが落ちている。一切れのシナチクだった。凍っている。くの字に横たわったまま左手を伸ばす。落ちているシナチクを摘んで口へと運ぶ。
口に含んでいれば凍った表面が溶けてゆく。そのまましゃぶり続けている。シナチクの味で口内が満たされてゆく。
もう店の者もカオリサンも、気配すら感じられない。どんより広がる雪雲の下、ただ雪原に一人横たわり、シナチク一切れしゃぶってる。
まだ少し眠たく、このまま寝ていたかったのだが、中断している仕返しついて、どうしたものか考え始めていた。
雪を全部崩してやろう、雪で店を埋めてしまおう。
初めから雪中に埋まった店だというのにおかしなことに、雪を崩して埋めてしまおうと考えたのだ。辻褄が合わないと気付いているようだった。それで、せめてその境界、今は雪原に表れた店との仕切、転じて敷居を寝たままで、素手で雪を掻き集め、押し均して埋めていく。敷居を掻き消すよう埋めていく。
では入る時通った開いたはずの穴、雪の洞はどうなったのか。自分が崩したのか、それとも自然に埋まってしまったのか。しかしどうも、今ここに横になっているのも、雪を掻き分け這い出てきた結果とみえる。雪の小山があればまだ、地下から地表へ這い出たときの盛り上がりと解釈できる。ところがただの雪原で、凹凸もなく、雪以外何もない。
遠くの山も見えやしない。白一色どこまでも、真っ平らな雪原が続くだけ。そこに一人、くの字で横になったまま、もう噛めるはずのシナチクをいつまでも、ちゅうちゅうちゅうちゅうしゃぶってる。
高い天井、落ち着いた間接光、やたらと広くとられた通路、壁面に大きく記された大文字のアルファベット頭文字とアラビア数字の組み合わせ。填め殺しの巨大ガラス窓から南西に広がる丘陵地帯が見渡せる。姉の入院した病院は昨年完成したばかりと聞く。それに比べて母の病院は築年数も経過している。くすんだ蛍光灯に低い天井、通路は狭く迷路状、偶々開いた小降りのアルミサッシ窓からは、迫る別館の外壁しか見えない。新館、東館などと称した後からの継ぎ足しが、病棟内を複雑にしている。今度は母が入院した。度々訪ねた母の下、記憶を頼りに病室までの経路を記す。
本館正面玄関から真っ直ぐ奥へと進む。突き当たり、左へ増築された通路がある。その通路口脇に階段がある。蛍光灯の光がリノリウムに反射して、そこはぼんやり淀んでいる。降りてはならない。降りれば霊安室へ通じてしまう。階段は二階へと上がっていく。二階へ出ると正面にナースセンターがある。まずそこで方向感覚が狂わされる。階段途中の踊り場で転換された所為もあるだろう。それと突然目の前に現れるナースセンターの位置、新館側東隅に位置しているのが感覚的に理解し辛いのではないか。錯覚が起きる。実は一階の入り口から進んだ奥はもう、地続きで新館になっているのである。新館一階の同じ位置にあたる場所、そこは開けた通路が確保されている。ところが二階の同じ位置では狭い通路に病室がぎっしり並び、ナースセンターのセンターという印象、角地にあるのに中心という印象が邪魔をして、いきなり込み入った入院病棟のど真ん中へ上がり出てしまったかのような錯覚がもたらされるのである。なるほど正面を無視して右手を見れば、確かに東館へと通じる通路が延びている。そこは隔たった新館と東館を繋ぐ、謂わば空中廊下である。互いの基址が異なる所為で、途中不意に斜行が起きる。両壁は迫り、低い天井のその通路を抜けた突き当たり、東館角部屋が母の病室である。
姉の病名は伏せたまま、母に姉の様子を話す。洗い物や何かと必要になるものなど、男の私より姉を頼りにしたいのだろう。
そうやって何度か足を運んだ母の病室。見舞う度、夢で通過した雪の洞、でんぐり返って反り返る、はっきりしない構造の、通路のことを思い返していたのである。
夢をみたのは5月4日(2010 5/4 )
2010年5月4日

