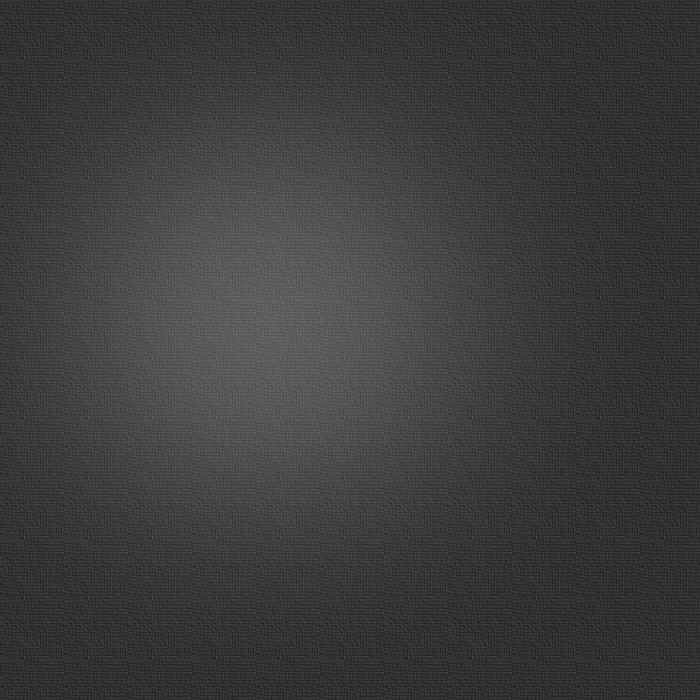秋の最後、静かに晴れたなだらかな丘陵を犬と歩いている。春先に死んでしまったニイカという犬を連れて歩いている。大人しく、ニイカは私についてくる。
勾配を和らげるよう見通しの良い斜面をわざわざ横切り、ゆっくりと、葛折に進んでいく。
その途中、右に折れ曲がってしばらく進んだ時だった。それまでしっかり握っていた引き綱がするると手中を抜けて、放れたニイカが勝手に先を行ってしまう。慌てて追いかけると、気付いたニイカが歩みを止めて、振り向いて私が来るのを待ってくれる。よくそうしたように、きょとんとした顔をして。
すこし息を切らせ追いついた私は、地面を引きずっていたニイカの引き綱を拾いかけた。と、それが引き綱ではなく、鎖に代わっている。重く冷たい金属の鎖になっているのである。何処ですり替わってしまったのだろうか。振り返り、今過ぎてきた斜面を見下ろす。すると随分下の方に大型犬が寝そべっている。以前流行ったゴールデン・レトリバーだ。飼い主の姿は見当たらないが、そのゴールデンは斜面に打ち込まれた白木の「繋ぎ棒」に結ばれて、のんびり昼寝している。鳥居を極端に低くしたような、あるいは木製の車止めのような形をした白木の「繋ぎ棒」。そこに探していた引き綱がきちんと二つ折りになって掛かっている。こんな時、いつもなら見つからず途方に暮れるところではないか。ニイカとだってはぐれてしまい、二度と出会えないのが常なのに、今日はこうして一緒にいることができる。
鎖を外し、元の引き綱に付け替える。そしてまた丘の上を目指して進んでいった。
どれくらいかして壁に当たると、今度は鴨居の上を小さくなったニイカが歩いている。突き当たった砂壁は安っぽい金粉を混ぜた壁土で、何色とも言い難いその壁の上の、天井近くにある鴨居を足場にして、子犬のニイカが、器用にちょこちょこと横移動してゆく。右へ、私の視界から右方向へと移動してゆく。
そんな時後ろが騒がしい。中年の婦人が二人、私とニイカの散歩について噂しているだけなのか、それとも主婦の勤めとして彼女たちもそれぞれの犬を散歩させているのか分からないが、二人にとって何か不都合な事が起きそうで声が大きくなっている、そんなようにも感じられるのである。そちらに気を取られ一瞬目を離した隙に、引き綱が白い扁平のたよりなげなゴム紐になっている。昔は「パンツのゴム」と呼んだ白いゴム紐である。伸縮するそのゴム紐を慌ててたぐり寄せたのがいけなかったのだろうか。それが随分長くなって伸びきった挙げ句、他のゴム紐と絡まって白く大きな団子となって目の前に転がっているのだ。こんがらがったその先は、ぷっつりと途切れている。
だからニイカを見失ってしまった。
すぐに探そうとせず、まずは絡まったゴム紐を一本一本解きほぐそうとしている。それが後ろにいる婦人たちの手前なのか、自分でそうしなければならないと思っているからなのか、はっきりしない。というのも、二人とも絡んだゴム紐には気も留めず、見失った犬を探して右往左往しているからだ。ところがその探している犬とはニイカなのか、それとも私は一度も見かけなかったが、彼女たちも犬を連れていて、その犬もいなくなってしまったから探しているのか、それがまた解らない。ただぼんやりと、ゴム紐が絡んで玉になってしまったことと、私とニイカの散歩がどこかで連関しているような、そんな気もして、引き綱とゴム紐を混同したまま、今考えてみれば二人の引き綱が交差している矢先に前にいる私が現れてしまって引き綱がこんがらかった、と解釈できなくもないのである。二人を追い越した記憶などないにも係わらず。
ニイカを探すゆとりができた頃、この部屋の様相がはっきりしてきた。ここは母の実家、小金井の祖母の家である。家の西側に位置するこの四畳半に壁があるということは、改築前の小金井の家だろう。床に着くことの増えた祖母が使っていた増築された部分、その入り口にあたる場所がまだ、鴨居のある砂壁で止まっているのだから。
その正面の壁から視線を右へ移すと隣の部屋、北側に位置する台所が見えるのである。四畳半と隔てる襖を外して、四人がけの食台を置いた台所が一部屋のように続いている。そして食台の椅子にはオヂちゃんが、いつものように片膝立てて腰掛けている。柔らかな、贅肉など全くない、か細い身体を少しだけ丸めて、上体だけこちらに向け座っている。上げた脚の踵を椅子の縁に引っかけ、立て膝に肘をかけたあの格好だ。ニヤニヤして、ずっとそうして私を見ていたんだろうか。
元気そうで良かった。さっき病院から退院してきたんだ、とオヂちゃんが照れくさそうに言う。
いや、オヂちゃんが言ったのではなく、「丁度今日退院してきたところなのよ。」と台所の叔母さんが話しかけてきたのだったか。
やっぱり何でもなかったんだ、こうしていつもと変わらずそこにオヂちゃんがいる。何を怖れていたんだかはっきりしなくなって、私は安堵してニイカを探すことに専念できるのだった。
ニイカ、ニイカ。私が呼びかけると何処か後ろの方で、くぐもった幽かな、子犬の発てる哀れな余韻を耳にしたような気がする。だがそれは気配だけだったかもしれない。
小金井の家では様々な動物が気ままに暮らしている。動物ではないが、小学六年生の女子児童が何人も混じっているほどである。そして、ニイカの名を呼んでいるうち姿を現したのは、そうした動物たちの中でも一匹の猫だった。
尻尾の先や耳の一部に斑が混じっているので白猫とは言い切れない、ほとんど白い猫である。ぴんと尻尾を立て、嫋やかに畳の上を歩いてくる。私が腰を下ろすと膝に懐く。すぐ慣れる猫に深い愛着など覚えようもなかった。それでも抱き寄せてやると大きな眼が近付いてきて私の鼻先をちろちろちろちろと舐め始めるのである。放っておくといつまでも止まない、びしょびしょになっても続けるニイカと同じ癖が猫にもあるものだろうかと訝ったが、確かに舌のざらつきがニイカとは全く異なるのだった。
と、そろそろさっきから若い女性の気配が左に溜っている。脚を崩して座っているのだろう、触れてはいないが私へ寄り添うようにして、仰向けになった猫を覗き込んでいる。「覗き込んでいるのだな」と、気配から存在の確信へと推移すると、その女性が果たして若いと形容できるか疑わしくなってくる。一回り歳の離れた従妹なのかもしれない。曖昧な年齢のその女性が猫の目について独り言つ。若い声である。
「大きな目だねぇ。ゼリーみたい。」
ゼリー。そう、フルーツゼリー。私もそう思っていた。ハート型の小さな容器から取り出したフルーツ味の蒟蒻ゼリー、薄い琥珀色したそんなゼリーが二つ、ぽっかりと空いた眼窩に詰め込まれているような、うっかりすると指を入れてしまいそうな、不自然なほど大きな眼。
「ほんと、ゼリーみたいだ。」
そう私も口にして意識すれば、ぷるるとしたその眼が実は凝固していて、表面に埃が付着しているのに気付く。さらに目をこらせば、色とりどりの砂糖粒だろうか、安っぽいパフェの飾りに使うような粒々が強膜下部に沈殿している。いや、その沈殿物は金粉だろうか。だとすればゼリーでなく、夜店のスーパーボール掬いの、中心に金粉を沈ませたミラクルボールなのかもしれない。いずれにせよ、本物ではないのである。
解っていくことで冷めていく。懐いてきたこの白猫に、私は冷めていく。
女の子たちが燥いでる。あの小学六年生の女の子たちだ。三人から四人くらいだろうか、台所西側の狭い風呂場に寿司詰めになっている。引き戸の僅かに開いた隙間から、ちらりとその様子が覗える。
初めから押し入れを探せば良かったのだ。そうすれば猫を構ったり少女に気を取られる必要もなかったろう。ニイカは鴨居の上を右方向へ移動していったのだから、この四畳半の東側、玄関へ通じる六畳間へ向かったに違いない。そしてその六畳間には押し入れがある。私の右後方にある押し入れに、きっとニイカは紛れ込んだのだ。そうに違いない、としかし、そんな事は端から分かっていたのではないか。最初からもう、押し入れにいると分かっていた気分が漂っている。
押し入れの中を覗くと、布団を積みかさねたその裏に、やはりいるのである。それで、ニイカ、ニイカ、と呼びかけるのだが、そこに横たわったままぴくりとも動かない。ふわふわした細い毛が波打つのも、私の吐く息の所為だ。紛らわしいことに、それは丁度、綿を抜かれたぺしゃんこの、子犬の縫いぐるみだった。
「オヂちゃん、面白い物を見つけたよ、ちょっと見に来ない?」
私が押し入れからその半身を戻して叔父に向かって話しかけた時、もうその押し入れは初めニイカを見失った部屋、家の西側にある四畳半の、後に祖母の寝室へと改装される以前の、砂壁にあたる部分に設えた位置へと変わっていた。だから半身を戻して私は右側にある台所へ向かい、叔父に話しかけているのである。叔父は先程と変わらぬ姿勢で椅子に腰掛けながら、いや、いい、いい、という身振りか、顔に皺を寄せながら右手を車の窓拭きの要領で素早く動かしている。そして続けて、何かを銜え、口を窄めちゅうちゅう吸う仕草を見せる。薬を飲まなくていけない、という意味のようだ。
顔色が悪い。表情は軽いのだが、鉛のように重く感じられる。見ると、座っている椅子の脇に脚輪付きの細い支柱が立っていて、支柱には澄んだ液体を入れた透明の袋がぶる下がっている。その袋からは透き通った管が伸びている。叔父が見せた仕草は、その管を銜えて吸うという事なのだろう。
最後に国立がんセンターへ見舞ったのは夏の半ばだったろうか。その時の様子、充電式自動点滴装置から蓄電池を使わない手動点滴に切り替えるのだと、点滴の毎秒落下数を数える叔父の姿が脳裏を過ぎる。
やっぱりだめだったんだ。
叔父を目の前にしながらも、夏の終わった最初の朝に他界した事実をどこかで受け入れていた。