1993年5月8日
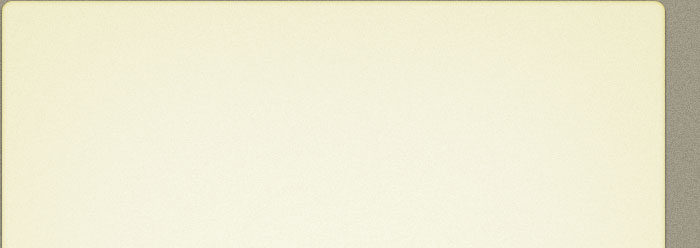

まさかこんなパーティーだとは思わなかった。
友達のパーティーがあるんだけど。そう誘われここに来た。
相手が女性でなくなっている。暗くてはっきりと見えないが、きっと白人男性だ。同室のもう一組は激しく抱き合い、白い液状のものが局部から溢れている。それを見て、自分も相手の口に向け発射する。快感ではなく、吐き気をもよおして出しているようなものだ。あたりに捲き散らされた液と、その濃い匂が、私を不機嫌にする。
気付くと明るい室内。どこにでもある普通の家。どうも家主が戻って来たようだ。だからみんな取り繕っている。娘がどんなパーティーをやっているのか、それは心配だろう。様子を見に忘れ物をとりに戻るくらいのことはしてあたりまえだ。間抜けそうにきょろきょろしたってなんの証拠も残ってない。でも、あなたの心配通り、確かに乱交パーティーだったのですよ。
そんなこともあって、いったん中断したのだけれど、丁度いい。新しい相手を探して次の楽しみを作るためのインターバル。だが往々にして邪魔は入るもの。
もう帰る、と言う。終電だから、と。
確かに送ってくれと頼まれたわけでもなく、一緒に来たからといって、一緒に帰らなくてはならない法はない。現に、私にまだ終電までの時間があることを知って、もう少し楽しんでいったら、と奨めるほどだ。ただ、言葉の裏で、一緒に帰ってくれるわね、と言っている気もするが、いや、そういうことを望む女でもないはずだ、と私は自分を混乱させている。
去っていく後ろ姿に向い、私ももう帰るから、と告げる。
それまで相手にしていた女に別れの挨拶をしようと、いったん外に出る。急がなければ追い付かない、と思いつつ、革の鞄についてその女から告白される。無視することもできず、話を聞いてやるが、こんなことでは駅までの道で追い付かないかもしれない。
案の定、一人でこの坂道を歩いている。ぐねぐねと緩やかにのぼっていくこの道は、小金井の祖母の家からの帰り道であり、経堂駅にもつながっているのだ。腕時計に目をやり、思ったより早いことに驚く。まだ十一時二十五分。
もうひとつ驚いたのは、この長いエスカレーター。しかも右にカーブしながら上っていく。高い天井。あの竹薮に囲まれた人通りのない上り坂からは想像もできない近代的な駅。私の知らないうちに経堂は変わっていた。もうここは経堂ステーションなのだ。
反対の下りエスカレーターでは、サラリーマンがぽつんぽつんと並び、そこをOLがジグザグに歩いて降りていく。そんな光景を見ながら私は、追い付いた彼女に質問した。さっき、あなたもやっていたのか、と。
本当はそんな話をしたかったんじゃない。ただ、なにか切り出さねば、と思い、つい口から出てしまったのだ。もう遅い。この間と、この笑顔の組み合わせは、彼女の敏感な感情を刺激している証だ。次に発せられるだろう、寛大になろうとして余計上擦る固い声。もう何度も出くわした場面。
予想通り、なるべく笑いながら、感情を読まれないようにと、彼女は話す。
それは夢だ、というのだ。私がパーティーで体験したことが、現実ではない、という。たしかにピーターのこと好きだけれど、そんなんじゃないし、そんな淫らなパーティーじゃなかった、という。
そうかもしれない。今こうして経堂ステーションに二人でいる実感を思うと、さっきまでの事とのバランスがとれないではないか。今夢をみているように、あれも夢だったんだと。だから私一人の体験であり、共犯者なぞいない、忘れてしまっていいものなのだ。だが、そうとして、何故あなたの感情が揺れなければならないのか。ひょっとして、同じ夢をみていたのか、それとも、私の夢を覗いていたのか。
理屈で考えれば途中下車したのだろう。いつこんなものが新宿に出来たのか。ここはビーチに仮設されたビア・ガーデンのようだ。靴の中に砂が入り込んでくる不快感を無視できないでいる。そう、パーティーを早めに抜け出したのは、これが目的だったんだ。終電なんかじゃない。きっとピーターに関係があるんだ。だってここはまるでアメリカじゃないか。
荒く大ざっぱにつくられた木張りの廊下をコツコツと音を発てて歩いていくと、奥の砂場で縫ぐるみショーをやっている。ふわふわし、手垢で黒ずんだ縫ぐるみは、恐竜というより幼児番組に登場する熊さんだ。これがジュラシィック・パークなのか。高いお金を払い、大人が楽しむものではないだろう。彼女が怒るのも無理はないのだ。しかしだからといって、それを大声で抗議することもなかったのだ。私の制止もきかず、つかつかと舞台に歩み寄り、悪態をついたのだった。自分達はいかに芸に悩み、日々鍛練に勤しんでいるか述べ、それを怠っているあなた達を許せない、と。案の定、店内の客は何の関心も示さない。ただ店側はそうは行かないだろう。商売を邪魔されて黙っていられるはずがない。マネージャーが出てくる。そんなことをいっていると、あなたはきっと後悔することになっていくだろう、と冷静に告げられる。もうその時には相手がマネージャーなのかウェイトレスなのかわからなくなっている。
二人肩を並べて店を出かかったとき、後ろからさっきのウェイトレスが追いかけてきた。何をするのだろうかと振り返ったとき、もう彼女は殴られていたので、とっさに私も仕返しをした、そのとたん、事務的な態度でマネージャーが手錠をかける。ここはあなたがたの国の法律と違い、こんなことをした以上、ここで働いてもらう、と。そう、これは二人を釘付けにする罠だったのだ。私まで巻き込まれたのだ。今までの彼等の言動は、全て計算し尽くされ、訓練されたされたものだったのだ。予告された通り、たしかに後悔することになった。
もうあきらめ、抵抗することもなくテーブルにつく。この世界で、しばらくは二人だけで生きていかねばならない。
それまでずっと一緒にいながら気付かなかったのが不思議だが、彼女の顔にはまだらのシミが出きている。もう中年女性なのだ。同時に二人いなくなってしまったのを、あっちの世界では問題になっているだろう、そして、皆に迷惑をかけているだろうと、どちらかがボソッと言う。
こうして面と向かっていて辛いのは、彼女の容姿の所為だけではないのだ。もちろん左目の義眼にはなかなか慣れない。笑うたびまぶたからはみ出してしまうのだから。だが匂は視覚より刺激的だ。口臭。原因は入れ歯にあるのだろう。不規則に並んだ大きめのプラスチックの前歯。時たまのぞく臼歯には赤や緑の詰め物が施されている。いつからこんな人工的になってしまったのだろう。
そろそろなのだ。むかし交した約束を、こんなとき、こんな目であなたを見てるときこそ、果たすべきだ。
「愛している。ずっと愛している。」
急に立ち上がって叫ぶ私を、あなたはどう思っていたのだろうか。
一九九三年 五月八日


