キリコをさがして
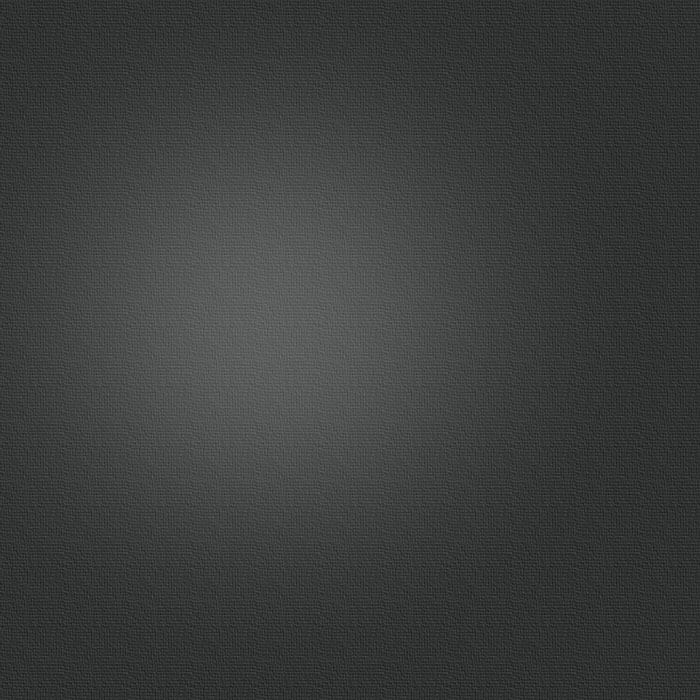
結局未明まで雑談していた。
サトコとキリコ。あとヒロアキと私。何をするでもなく、二階の私の部屋で一晩中ぐずぐずしていた。もう口論にはこりごりだから、四人とも暗黙のうちに、肝心な事には触れないようしていた。でもそのくせ蟠りは消えていない。それぞれが互いに、口にはしない、不満を抱えていた。
帰ってくれとも言い出せず、かといって、このままこうして朝を迎えればもっと疲れてしまうだろう。状況を変えるためには、私がじっとしていてはいけない。みんなが諦めて帰ってくれるよう、仕向けなくてはならない。
とりあえず下の様子を見に部屋を出た。階段を降り台所を覗くと、母がもう朝食の準備をしていた。こんなに早くから母が起きてるなんて、めずらしい事だ。まだ外が暗いから蛍光灯をつけて台所にいるという変な朝。これは子供のころ、遠くに出かける時とか、何か特別の日の暗いうちから出かけの準備をする、期待と寝むけの入混じった見慣れぬ光景とそっくりなのを思いだす。
どうしてこんな早くから起きてるの、と尋ねようとして、どやどやと音がするものだから振り向くと、サトコを先頭にみんながぞろぞろと階段を降りてくる。そして、母に挨拶しているではないか。どうも母は気を利かせて私達の朝食の用意をしていたようだ。そんな必要はないのに、むしろ私には迷惑だ。こんな事に親を巻き込みたくはない、そう思いながらも、母が昨日の晩からこうなることを予想して暗いうちから起きて台所に立っていることが痛ましく、せっかくの母の気持ちを台無しにするわけにもいかないだろうと、結局はみんなに朝食を勧めざるを得なくなる。早く帰ってもらうつもりが、それどころでなくなってしまった。
いつもなら時計替わりのテレビをつけて、一日の始まりを意識させる活気のある食卓も、こんな時間だと雨戸もカーテンも締め切って、夜中と何の変わりばえもしない。私はブラウン管に朝日が差し込み、ブラウン効果が太陽光線で相殺されるのが朝だと思っている。男女のキャスターが爽やかにニュースを伝える、そんな番組はおろか、きっと今テレビをつけても電波調整画像と音声基準信号が受信されるだけだろう。もう何も話題にすることがなくなり、ただ黙って食卓につく。目の前にサトコ。そのとなりがキリコ。だからヒロアキは私の隣に座っている。母の手前取り繕ってはいても、内心もう誰の顔を見るのもうんざりしている。
こんな時に気を使うのは、もっと疲れる。実家で家族と暮らしていると、外の人間と家族とが一緒にいる空気感が、どうも好きになれない。しっくりこないのだ。やたらと無駄な気を使ってしまう。気を許した友人ですらそうで、ましてや仕事がらみだともっとそれがひどい。小学生のころ、家族と外出するのが嫌になったことがある。外で家族といるところを同級生に見られたくない、という感情が芽生えたからだ。それまでは母に買い物へ連れて行ってもらうのが楽しみで、ちょこちょこ付いて行ったのに、あるときからぱったりと止めてしまった。基本的にはあれからずっとそうなのだ。今でも家族と外の世界に出ることには抵抗があり、どこか自分に無理しているところがある。内と外の接触は私に無駄な気を使わせる。
ただですらそんな気分でいるところへ、母が私に用事を言いつけるものだから余計、どうしようもなかったのかもしれない。付け合わせに使うから、庭の、隣の敷地に生えている鳥草(トリクサ)を採ってきてくれないかと私に頼むものだから、もう我慢できなくなってしまった。今までのキリコやサトコ、ヒロアキに対する不満と、母の私への要求が重なって、急にとどめがたいほど激しく強い感情が沸き上がり、ついに怒りが爆発してしまった。みんなが見ている前で突然、生野菜を盛った皿を取り上げ、思いきり床に叩き付けたのだった。音もなく瞬間の事だったから、私が気をとり戻した時には、足元でサトコがしゃがみこみ、後始末をしながら私の顔を見上げているところだった。鋭利な陶器の破片と、くたっとした緑葉野菜の組み合わせが似合わないし、それを慎重に仕分けしながら同時に私の顔を見つめるサトコの視線が、不可解なものに対して距離をとろうとするときの、あのわざと冷静に、淡々と複雑な仕事をこなして行く、あて付けがましい態度とあべこべで、とても気持ちが悪いものだった。けれどそれは、私のしたことが周りをそんなふうにするだけの、充分軽蔑に値するものだからだとわかって、その上でそう思っている。この不均衡な状況を作り出してしまったのは誰の所為でもない。他ならず、私の所為であるのをちゃんと自覚しているからだ。そういえば一昨日、久しぶりに会った友人が私を「直情的」であると言ったけれど、今思うとなんか予言めいている気がする。極端な解釈だけれど、ひょっとすると、その彼が私をこうさせてしまったのではないだろうか。私を暗示にかけてしまったんじゃないだろうか。でなければ、こんなつまらない事で雰囲気をぶち壊すようなこと、するはずがない。
中断された食事。キリコもサトコを手伝い、割れた食器の破片を拾ってる。狼狽する母を宥めるつもりだろう、わざと何でも無いことの様に振る舞い、笑顔で母に雑巾のありかを聞いている。彼女らしいやり方だ。でもそれは、私のやったこと、いましがた起きたことが、母への感情ではなく実はキリコ達に向けられた感情、苛立ちの証であると気付いているからこそ、とっている態度なのでもある。私にしてみればそれが余計不愉快なのだけれど。一人ヒロアキはそれを見ないように、うつむいて食事を続けてる。私はといえば、つっ立ったまま、しゃがみこんだサトコとキリコを見下ろしている。
家でこんな醜態を晒したのだから、みんなには一足先に行ってもらうしかなかった。私が遅れて井の頭公園に着いた時には、もう花火見物も終わり近いころだった。
時々行われる季節はずれの花火大会。井の頭公園では、池の真上を会場にする。一風変わった花火見物だ。大勢の見物人達は池の周りをぐるっととり囲み、静かに鑑賞している。私の位置からは何も見えないから、花火でなく能をやっていたとしても何の不思議はない。でもそれより奇異なのは、足場にする渡し簀の子が泥だらけで、服が汚れるはずなのに、みんながきちっと着座していることだ。私にはとても理解できない。これだけの人がいて、汚れを気にする人は誰もいないのだろうか。
脱いだ靴を受付に預け、人垣の中、先に行ったキリコたちを探す。この広い池のどの辺にいるのかわからないし、こんなに多くの見物人の中から、はたして彼女たちを探し当てる事ができるものだろうか。半分諦めながらも対岸の、池の南側へと向かっていく。
歩いているとじわじわと泥水が靴下に浸み込んでくる。渡り板がところどころ池に漬かっているからだ。始めは気持ち悪かったが、慣れてしまうと、だらしのない、もうどうでもいいやという投げやりな気分になり、たまには浅くなった所など、わざと泥池に足をつっこんで歩いたりもした。
池を横断しきる前に見せ物が終わってしまい、それでのろのろしてるうちに見物人が帰り始め、とても人を探すどころではなくなってしまった。泥の跳ね上がった狭い渡り板は、出口へと向かう人でごった返している。私がその通行を妨げていると思い、どうしていいかわからず、とりあえず道を譲るため、池に降りるしかなかった。大勢の帰り客の中、私は一人両足を泥沼に浸けて立ちつくす。
考えてみた。冷静に私がした事を考えてみた。サトコやヒロアキはともかく、少なくともキリコとはもう一度会って、話をしなければいけない。彼女を探し出してさっきのこと、いや、もっと遡って今までのしてきたことを全部、謝らなくてはいけないと感じ始めていた。なんてひどいことをしたんだろう。単に皿を割ったんじゃない。もっと大切な物を壊してしまった。じっくりと時間をかけ積み上げてきたことを、私は一時の感情で台無しにしてしまった。培ってきたものをぶち壊された彼女の気持ちを思うと、どうしようもなくすまない気分になり、心の痛みに苛まれる。こんな感情を私は忘れていた。大げさに言えば人を慈しむような、そんな心を失いかけていたんだろう。キリコに悪いことをしてしまったのだ。
ぼうとしてたから、先に向こうから声をかけられた。きっと彼は随分前から私に気付いていたんだろう。ケイ氏も三人とは別に、一人でこの催しを見物に来ていたようだ。帰り客に混じって私へ手を振っている。
ケイ氏には作曲を依頼されている。ここのところ何曲も提出しているが、一向に埒があかない。ろくな曲ができないからだ。この間渡した分も、きっとだめだろう。彼の気に入らなかったに違いない。自分でもいいと思ってないもの、人が気に入るわけがない。
彼が私に気を使ってくれているのがわかる。言い回しに悩んだり言葉を選んでいるわけではないが、間のとりかたとか、ゆっくり穏やかに話すとか、私を刺激しないように、時に視線を反らし、笑顔をみせながら、この間のあの曲がだめであることを告げる。ケイ氏が人に気を使うというのは余程のことである。普段はもっと単刀直入な人柄だ。それなのにこんな気の使い方をするところを見ると、もう私がどうしようもないところまでいってしまったと、彼も見抜いているんじゃないだろうか。私を傷つけて余計悪化させるより、少し宥めて何とか仕事させてしまわないと、彼自身の身も危なくなってしまうのだろう。
私はいい曲が書けないことを詫び、もう一度だけ機会を与えてくれるようケイ氏に頼んだ。今週中に仕事するから、そして今度の曲がだめだったら、私を切り捨ててくれ、そっちにも迷惑はかけるが、ほかの作家を探すなり、既にある曲を使うなどして、回避してくれ、と頼みこんだ。思いつきで言っているわけじゃない。ここ数日、ずっと考えてきたことだ。もうだめかもしれない、もう何もできないかもしれないと、どのみちこの仕事を始めたときからそんな感じがして覚悟していたから、それがいつになろうと、仕方ないことなのだ。今度が最後になる、長いこと続けてきた作曲という仕事も、次で終わるのかもしれない。せっかくここまできたのに、たった一曲の所為でやめていかなくてはならない。私は表現するという意欲を失いかけている。もう情熱もない。きっと次もだめだろう。ケイ氏との約束は、賭けに外れることを承知した、最後の切り札だった。
ケイ氏と別れたころには会場から人は減っていた。キリコたちもここにはもういないかもしれない。このままではどうしようもないので、ともかく靴を履こう、靴がなくては外を歩けないではないかと、預けていた受付を探すのだが、どうもその受付が見あたらない。
会場のあちこちを行ってみたが、それらしきものはない。探しているのは受付だが、自分にとって本当に必要なのは受付ではない。靴があればいいのだ。私の茶色の運動靴さえ見つかれば、受付などなくたっていい。そういう道理から私は靴を探し始めた。
きっと透き通ったビニール袋に入れられて、あの靴はちょっと大きめだから無理に詰め込まれて、どこかにおいてある、例えば客席の後ろの方の照明卓の下あたりに、まだ残っている三人連れの女性客の足元の陰に、ひょっと取り残されている、他人が間違えて履いて帰るはずないから、絶対どこかにある、思いつく所を虱つぶしに探した。
勘違いしていたかもしれない。受付に預けたんじゃなく、袋に入れて自分で持っていたのかもしれない。だとすれば、さっきケイ氏といた辺りがあやしい。あの辺に置いて忘れてきたのかもしれない。
池の上のはずのその場所に戻ってきたころ、もうそこはホールになっていて、丁度次の催し物が始まっているところだった。○○トリオだ。メンバーの一人、ジョーユさんを知っているから、すぐわかった。ジョーユさんは国立で「はっぽん」というお店をやっていて、昔そこでその人の歌の伴奏をしたことがあるからよく知っているのだ。○○トリオもまだ続けていたんだ、と、妙に感心し、細々とでも続けているこの三人組みをあらためて見直してみた。マイクを持って三人がばらばらに歌っている。ベースもギターもないのに、ロックンロールのサウンドになっている。バンドというよりお笑いのコントをするトリオだったかもしれない、忘れてしまった。初期のビートルズっぽいサウンドを聞きながら、私はロビーへ出た。ずっとつきあう気にもならなかったからだ。
杉並公会堂の売店まで靴を探しに来たんじゃないけれど、もうさっきから老朽化した公会堂、杉並公会堂の中にいることになっている。動き回っているうちに屋内空間の迷路にほうり込まれていたのだ。靴を履かずにこんな場所をうろうろするのは、本当に落ち着かない。冷たいコンクリートの床は、靴下だけで歩くものじゃないし、他人が皆靴を履いている中、私だけが靴下姿でいるのは変だ。なんか一人だけ裸でいるような感じすらする。
井の頭公園のさっきから、幾つもの部屋を抜けてきた。分厚く重いパッキング付の扉を開けては、次々と部屋を移動していた。それは、まるで廊下のように一つ一つが繋がっているスタジオのようだった。防音用の二重扉は、その狭い中間地帯も部屋と勘定してしまうから、思ったより動き回っていなかったのかもしれない。音響調整室の低い扉をくぐり、明るい廊下に出た所で、偶然この売店を見つけた。探していた訳ではないけれど、せめて売店なら受け付けのこと、ひいては靴のありかを知るきっかけを掴めるかもしれない。
最近見かけなくなった瓶入の牛乳や、キャラメル、変なパン、多分メロンパンなんだろうが、そんなものが鈍い蛍光灯に照らされ、飾りけのないガラスの陳列棚のなかに収まっている。懐かしい森永、明治、フルヤ、東鳩。製菓会社の印や社名が、地味な公共施設の内装では浮いて見える。古くさい紺色の制服を着た女性販売員が、専用のキリでオレンジ牛乳の蓋をポンとあけていた。ギュウブタだ。これを集めるのが流行ったことがある。そんな事を思いだしたからか、売店の奥の喫煙所にミヤケ・イシハラさんがいるのに、そう驚くこともなかった。二十年ぶりに会うミヤケ・イシハラさん。彼女はスタンドバーの、背の高い円形テーブルの上に直に座っていた。ハイヒールに短いスカートで、脚を組んで座っていた。
子供の頃と比べて肉付が良くなっている。二十代の彼女を見ていないから、これでも最近太ったのかもしれない。でも決して老け込んでいないし、三十半ばの女らしい豊満な身体は魅力的だった。小学校五年のとき彼女は転校してきた。中学も一緒だったが、卒業後それきりで、会ったことはない。
彼女が私を気にしていないのをいいことに、いつの間にか首から下げていた一眼レフでファインダーを覗く。プラナーの中望遠レンズが斜めから彼女を見つめる。コンタックスの明るくきらきらするファインダーで輪郭をなぞり、スプリットプリズムの二重像合致で、分段されていた瞳を一致させる。肉眼では感じられなかった端正な顔が、適正露出マークとともに浮かび上がる。彼女がこちらを見つめる。シャッターは切らなかった。絞り開放の、背景が美しく飛んだ映像で被写体を凝視するだけでいい。
一眼レフは二重三重に屈折した鏡だ。レンズを通った映像は上下左右に反転し、それを鏡で反射させ、さらにペンタプリズムを通過させ正像にねじり戻す。私が今ファインダーを通して見ている人は、裏返しの反対の、そのまた裏を反射させ、反転して元にもどったミヤケ・イシハラさんだ。ミヤケ・イシハラはラハシイ・ケヤミになり、それがイシハラ・ミヤケになる、そしてその逆行、ケヤミ・ラハシイ、ミヤケ・イシハラ。
だから度々私は、反転したイシハラさんを相手に話をしていた。彼女ならイシヤマさんのことを知っているかもしれないと思ったからだ。イシハラさんはイシヤマさんとは仲がよかったはずだ。
子供のころイシヤマさんが好きだった。目と口が大きくはっきりとしていて、そのくせ体は華奢で痩せた、ひょろっとした色黒の女の子。まだ眼鏡を掛けてなかったけど、近眼になりかけていたのか、遠くを見るときはよく目を細めていた。そんな子を好きになった理由を、自分でも思い出せない。子供時代の事だから忘れてしまった、というんじゃなく、どうもそのころから、あまり理由は無かったんじゃないだろうか。彼女の特徴を思い描いたとき、どう考えても好きになる要素がないのだ。子供といっても、もう十二歳になれば容姿の美醜は確定してくるし、それを判断する感覚も、そんなに大人とは変わらないはずだ。なのに彼女には、あまり美しい、かわいい、といえるところが見当たらない。事実、友達に胸の内を証したとき、その友達は気がしれないと、どこがいいのか、と私の「好み」にまったく理解を示さなかった。その友達はと言えば、私の席の隣の、ミヤケさんがいい、と言っていた。それは私にも理解はできた。確かにミヤケさんはちょっといいとこがある。でも私はだめだ。ミヤケさんには「中身」が無い気がしたからだ。隣の席で仲は良かったけれど、それこそ今の感覚でいうところの異性への意識というものはなく、ただのクラスメイトと割り切っていた。イシヤマさんはどうかというと、なんかちょっと他の児童とは違う、表面には見えない、言葉にならない魅力というものがあった気がするのだ。それが私の勝手な思い込なのか、思春期を前に、とりあえずのでっち上げで相手を想定するだけの対象だったのか判らないが、ひょっとすると今でもその謎を解く為に、彼女との再会を望んでいるのかもしれない。大人になってどうなっているか、この目で確かめたい。また、そのころの私をどう思って見ていたのか、じっくり話をしてみたい。
私を相手にしているのかどうか解らず曖昧なまま、イシハラ・ミヤケさんは、静かにゆっくりと本でも読み聞かせるようにイシヤマさんの消息について語り始めた。私の方に向き直ることなく、奇麗な形のいい脚を組んだまま、売店を見つめながら、そうねー、彼女はねー、○○してそれで、こないだも会って、○○なんだってー。私は彼女が腰掛けているテーブルに肘を付きながら相槌うっている。中身の無い話に聞き入って、懐かしい、淡い思い出を、勝手に追いかけている。キリコも靴もどうでもいい。イシヤマさんの事を考えているだけで、今は落ち着いている。ただ一方で、話しているイシハラ・ミヤケさんではなく、正像のミヤケ・イシハラさんに変な関心があることを否定できない。それは子供のころ見た夢に関係があるようだ。丁度さっき話した、ミヤケさんを好きだと友達が告白したから見た夢だったと思う。まだ性の知識が全く無かったのに、変な夢を見た。
私が家の風呂場で体を洗っていると、ミヤケさんがふうっと入って来たのだ。狭い洗い場に裸で二人きりになる。彼女はタイル張りの浴槽の脇の、シャワーをしつらえた部分に全身を晒して立つ。そのころ私は同年代の女子の裸なんか知らないから、姉と一緒だったころの、前見た姉の裸を重ねたんだと思う。全裸で目の前に立つミヤケさんは、よおく見て、見ていいよ、と私に言う。足首から、すらっとした足から徐々に視線を上へ移してゆく。男子の私のようには付いていない、あの部分で止まる。そこには纔なすじ、不思議な切れ目がついていた。恥ずかしがるどころか、彼女はみせびらかし楽しんでいるのようだった。次の瞬間しなやかな細い身体をくるっと丸め、彼女はしゃがみ込んだ。そこで曖昧になる、よく分からなくなる。
女性の部分がどうなっているのか知るのは、それからずっと後のことだ。だいいち、そのころは男と女が抱き合う意味も、その行為そのものも知らなかった。だから目が覚めた後、それがいやらしい夢である事は解っても、何を暗示しているのかさっぱり解らない。その日の朝、学校でミヤケさんと会ったとき、変な感じだったのを覚えている。いつもと違うまなざしで彼女に接してしまったのだ。私にとってその夢は、不可解で気味の悪いものだったから、それが現実の彼女の容姿に潜む得体の知れない何かの所為だと疑ったんだろう。イシヤマさんが出てくるならまだ分かるが、特別な好意を持っていないミヤケさんが出てくるのは思ってもみぬことだったのだ。異性への分裂する愛と性。今なら簡単に解釈することを、子供だった私は怪訝なものとして、どう扱ったらいいのか判らず、ただ避けようとしていた。ミヤケ・イシハラさんとはミヤケ・イシヤマさんの意味なのだ。私の無意識は分岐する二人を捻ってひっくり返して、大人の姿で再現させている。
キリコを捜し、靴を探し、結局はこの杉並公会堂、子供のころから時代遅れでボロボロだった公会堂で、ミヤケ・イシヤマさんに会ってしまったのだ。しなければならない事、今自分が置かれている状況を忘れ、懐かしい小学校時代の思い出に酔いしれている。悪い感情は無くなってしまったが、いつまでもこんな所でまどろんでいていいのだろうか。
閑散とした売店脇の喫煙所でミヤケ・イシヤマさんははなしつづける。
「彼女はねー、○○でねー、~~したんだよ、それでね、今はね・・・・。」
一九九五年五月二二日
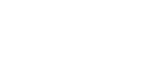
1995年5月22日
キリコをさがして

