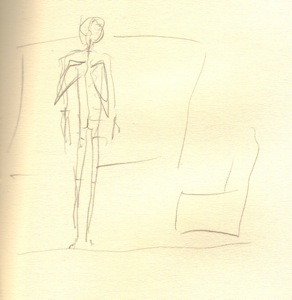食用天使
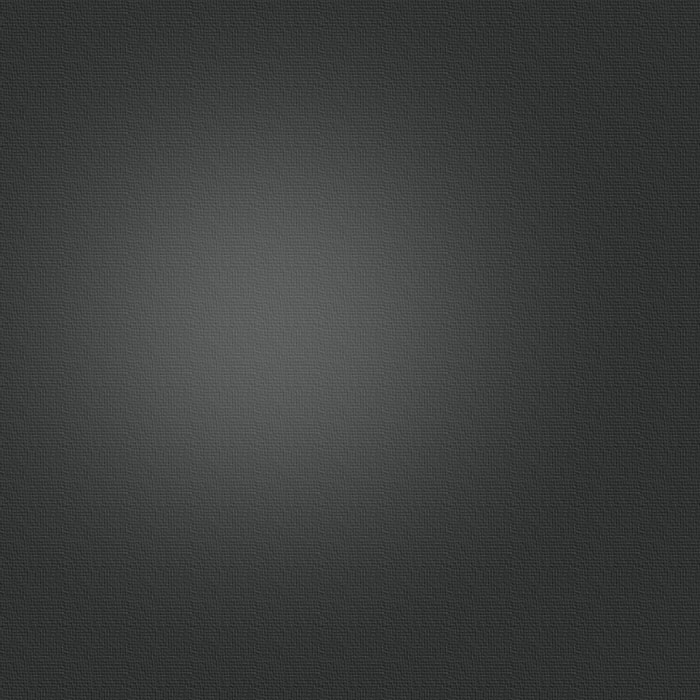
天使だとは思っていなかった。
毛むくじゃらだったし、今まで羽に気付いていなかった。
食用にしているこの動物は、頭から足の先まで全身が毛で覆われている。子犬のようなふかふかした柔らかい黒毛だ。だから哺乳類だろうとは思っていた。ずっと食用として扱われているからあまり意識したことはなかったが、大きさも姿形も人間に似ている。かと云って猿に近いと感じたことは一度もない。ひょろっとした体、人間並の脚の長さの所為かもしれない。
その食用動物を何体か買い込んでいた。さっき一頭を食べ終えたところだ。二階の部屋で一人、ここのところ食用動物を貯め込んで暮らしている。
生きたまま食べるのが普通である。それなら飼っていると言えなくもないのだが、生きているようにも思えないのが不思議だ。多分長い間に食用へと改良された結果なのだろう。仮死状態で出荷され、そのままの眠った状態で生存するよう作られているのだと思う。それで逃げたりしないし、食べる直前も暴れたりしない。痛みも感じていないようだ。人に喩えると寝惚けたような状態が続いているのかもしれない。まず俯けに寝かせる。そしてふかふかした毛に隠れた背骨に沿って、首の付け根から尻までを真っ直ぐナイフで長い切り込みを入れる。彼らはその間中ずっと大人しくこちらに背を向けている。それから、その長い切り口からフォークで中の肉をほじくり出し、食べるのである。あと両膝の裏。ここは横に切り口を付け、やはりそこから剔るようにして肉をほじる。肉をほじっている間もじっとしている。そういえばいつもその動物の背中側しか目にしていないことになる。だから、どんな顔をしているのか知らない。保存中、即ち仮死状態の時偶然見かけたことはあるが、毛に覆われた顔は確か、目を瞑っていた。
ところで肉は何も付けずに食べる。温く、ぼんやりした、癖のない味だ。美味いのかと訊かれるとよく分からない。もう慣れてしまって、味について疑問を感じたことなどないのである。ただ敢えて似た味を挙げるとすれば、なるとまきだろう。中華そばにのっているぺらぺらのなるとまきの味だ。歯応えは全く違っているが。
一頭を食べ終わり、続けてもう一頭食べたくなった。切り口から掻き出せる肉の量は少なく、綿を抜かれたぬいぐるみのようになっても満腹にはならない。それで廊下の向こうの、今は使われなくなった和室からもう一体選んできた。
それは多分、雌なのだ。他の個体とはどこか違っている。優しさを感じ取ったのかもしれない。食べるためのものなのに、奇妙なことに、愛おしさに近い感情まで抱いてしまった。それも変な話で、生きて活動しているわけでなく、ただ棒のように硬直したそれなのに、いったいどう感情移入できたのか自分でも分からない。ただ、優しそうな感じがした、としか言えない。だから背中に切り込みを入れて中の肉を食べた時も、罪深いような、温いその肉の味が何か嫌なものを食したかのような、そういう気分をも味わってしまっている。これを食べていいのか、今日初めて自身に問いかけたのである。やはりこの個体は後にすべきだったのかもしれない。選ぶ時迷ったのだ。生かしておくこともできたのに、ちょっと雰囲気の違うこれを食べ始めたことで、食用動物というものへの気持ち自体が変わってしまったのだ。
後ろめたさを感ずるのはその所為だけでもない。実家の二階に一人で籠もり、下には内緒で肉を食べていることとも関係している。この動物を食べる習慣は広く知れ渡っている。だが、五十を過ぎた独り者が密かに食べるとなると、端から見てどこか異常に感じられる気がするのである。あまりいいことではない、そう自分が感じるのである。
そのくせもう手を付けている。頬張って、生肉を噛んでいるのである。ナイフとフォークを握ったまま。
その時は二階の一番日当たりのいい部屋にいた。以前はテレビなんか点けてみんなで過ごした部屋だった。今は片付け、なるべく物を置かないようにしている。その部屋の北側にある入り口、扉の側に立っている。南側の大きな窓が正面に見える位置だ。右手の壁にソファーが置かれている。そこに俯せに寝かせて食べていたのである。
なかなか飲み込めなくて咀嚼を続けている最中だった。そんな事は初めてだったが、その動物がすくっと立ったのである。
背中にも膝の裏にも切り筋をつけたまま、窓の方を向いて直立している。私からは背中しか見えないが、多分ぼんやり、南側の窓から外の景色でも眺めているのだろう。ただじっと、立っている。
まだ動けるのが不思議だった。確かに食べ始めたばかりだが、もう肉片はいくつか穿り取ってしまっているのに。こんな状態でも大人しく生きている。痛がりもせず、緩く開いた背中の切れ目を晒したまま窓の外を見てるなんて。
あれ、羽が生えてる。小さいけど。
肩の下、かいがらぼねの辺りから羽が生えているのだ。切り筋を中心線に、ほわほわした黒毛に覆われた小さな羽がぺろっと、子犬の耳みたいに垂れている。
そうか、天使だったのか。
世間ではそのような言い方をしていない。でもこれは食用天使なのだと理解した。今までずっと、天使を生食していたのである。酷い事をしていたのかもしれない。さっき口にした肉片はまだ噛み続けていたが、味が解らなくなってきた。味わうよりも、感謝しなければならないような、彼らの痛みは私たちへの慰みそのものだったと、咀嚼しなければいけなかったかのような。
ふっと彼女は動き出す。こちらには背を向けたまま窓の方へよっていく。そして外へ落ちるよう窓から出て行ってしまった。追いかけるでもなく、私も南側の窓に歩み寄り外を見た。できれば一度、顔を見ておきたかったのだ。
もう塀を乗り越えて、お隣のイトザキサンチの瓦屋根に乗っている。そして左側に向きを変えた時だった。一瞬こちらを振り返ったのである。それは少女の顔だった。円らな黒い瞳だった。微笑んでいるようにも見えるような。
思わず私は手を合わせていた。そして彼女を見つめたまま軽く頭を垂れた。心の中でごめんなさい、と、静かに詫びながら。
彼女にそれが伝わったか分からない。そのまま左方向、東へと彼女は移動していった。
2009年 10月26日
2009年10月26日