ラーメン
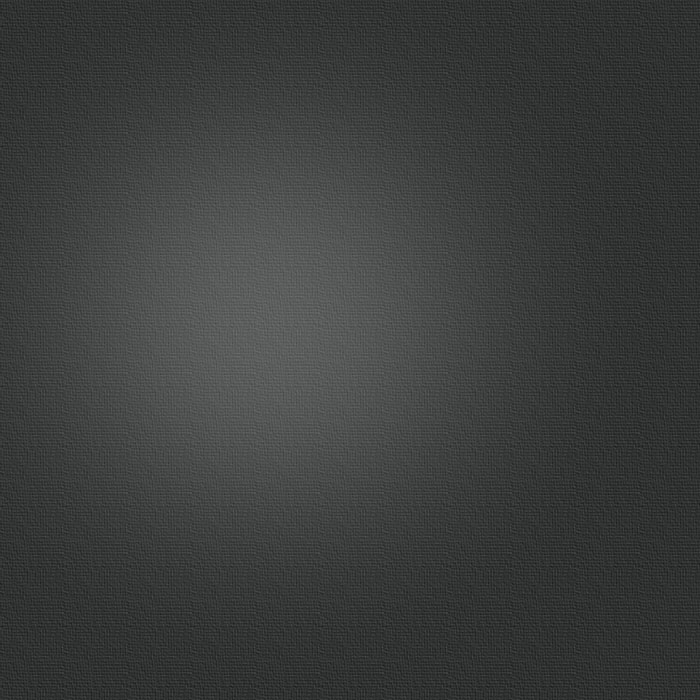
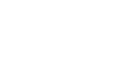
受話器を持っているわけでもないのに相手は見えない。苛立っているのは私だ。あなたはだれかに語りかけている。
何が許せなくなっているのか自問してみる。話し方。声色。あなたの声そのものが、ほとほと嫌いになってしまった、もうあやまるしかない。そう思うと同時に、私は床に手をついていた。全てを話し、別れてもらおう。
どんなに傷つけてしまうだろうか。どんなに悲しませてしまうか。この数年間、わたしはこんな場面を想像しては思いとどまっていたのに。
なのにあなたは平然としている。どうせあなたの子供はこの先も存在することはないのだから。現実の君とは似つかない、痩せた、冷たい顔の女がそう言う。
そうだろう。君の言う通り、別れて他の人を愛したとしても、未来の、私の子供の可能性を君に握られていては、その分孤独になっただけなのだと思う。歩きながらたったひとりでそう考える。
この季節は朝になっても夜のままだ。もうすぐ六時だというのに一向に夜の明ける気配がない。荻窪の北口。線路沿いのこの道は特にラーメン屋が多い。こんなことになった前の晩から、何も食べていなかったのだからちょうどいい。 普段は行かない、通りの終わりにある店に入ろう。ほんと、ここのところあの店には行ってないんだ。やってればいいんだが。
まだ暗い荻窪銀座通りを阿佐ヶ谷方面に歩く。昔踏切があったこの位置まで来ればもう店が見えるはずだ。
明りが消えてる。やはりこんな時間までは営業してないのか。それとも定休日だったのだろうか。
引き返すことにした。
駅へと向かう道の両側には、ラーメン屋を兼ねた旅館が数軒ある。そんな中で気を引かれたのが、出来たての、造りかけのホテルだ。駅に向かって右手にあるこのホテルに、今まで気付かなかったことが不思議でしょうがない。ここは住み慣れた町であると同時に、二度と訪れることのない懐かしい温泉街でもあるのだろう。
迷っているうちに駅に近付いている。暗い朝だというのに人は多い。さっきのあの店でいいじゃないか、と、ふと思う。工事中かもしれないが、あの近代的なホテルだって他の旅館と同じように、きっと一階はラーメン屋に違いない。人の流れにあわせるようにしてまた来た道を戻る。
人ごみの合間からあの人を見つけたとき、意外にも私は動揺しなかった。それは体験済みのこと、昨日の夜の反転だったからかもしれない。小さなリュックと毛糸の帽子。別れたときと同じ格好でホテル入り口前の縁石にちょこんと腰を下ろしてる。現実では私がそうだった。イレーナ・ホールの前で、あんな風に、いまのあなたがいる位置からいまのここ、私がいる、この方向に向かってあなたを見送ったのだ。あのとき私はせつなかったよ。もっと一緒にいたかった。でも、今は違う。もうわかってしまったから。
実はさっきから気付いていた。後ろを彼が歩いているのを。引き返そうとしたとき見たようで、そうじゃなく、きっと感じただけなのだろうけれど、私は気付かぬ振りをしてずっと歩いていたんだ。別に卑屈になってそうしてたんじゃない。ただ、感じていればそれでいいと思ったから。だから今もあなたに声をかけたりはしない。私に気付かないあなたたちでいい。
私が知っている事実というのは、昨晩彼が打ち合わせだと云っていたこと。昨日ホールからなかなか出てこなかった。きっと随分前からこのホテルを予約してたんだろう。二人で過ごすこの夜を、本当に楽しみにしてただろうに。計画は失敗し、彼はこれなかった。仕事をふってまで女との時間を持とうとする男なら、きっとあなたも惚れたりはしない。だから一晩中ああやって待っていたんだ。家内と私との時間の一方で、あの人はここで、幸福な想いに満たされながら彼を待ち続けていた。そう思うと、私の胸も寂しさでいっぱいになる。でもあなたは幸せだ。もうすぐ長い待ち時間も終り、彼と出会うから。そのことを本人達より先に、私が解っている。イレーナ・ホールの前で別れてから、この時間までというもの、きっとあなたたちにとっても長い夜だったのだろう。
開店したてにかかわらず、店内は混雑していた。どのテーブルも人がぎっしりで、席に着きようがない。初めての店には、いつもあの独特な場の力が新参者を襲う。その場に慣れず、席に着けずにいる私に向い、容赦なく注文をとろうとする中年の女給。焦りながらも、ふと、白く濁ったスープに青菜をのせた◯◯麺をすする男性客を目にした、そのときだと思う。後ろからあの男が声をかけてきた。
やはり後ろにいたのだ。そして彼等もこの店に入った。私が座る場所を探してぐずぐずしてるうち、あとから来たにかかわらず、二人はちゃんとテーブルにつき、しかも注文すら済ませてしまったようだ。
なんにした?
彼はうれしそうに聞く。私が今ここにいること、要するに、偶然こんな所で会ってしまって、もう少し驚いてもいいはずなのに、彼はただ、なんにした、と聞くのだ。
◯◯麺にした、とちゃんと私は云っただろうか。もうはっきりと覚えていない。そんなことより別のことで頭がいっぱいだったから。それは正直に言って彼への劣等感だ。あいた席を素早く見つけ、迷わず注文を出せる判断力。私の持ち合わせない才能。それに比べて私はどうか。混雑した店内で未だに立ちっぱなしでいる。活気のあるこの場でひとり浮いてる。無様だ。つくづく自分でそう思う。そんなことで頭がいっぱいだったのだ。
一九九三年十二月四日


1993年12月4日
ラーメン
