カノン
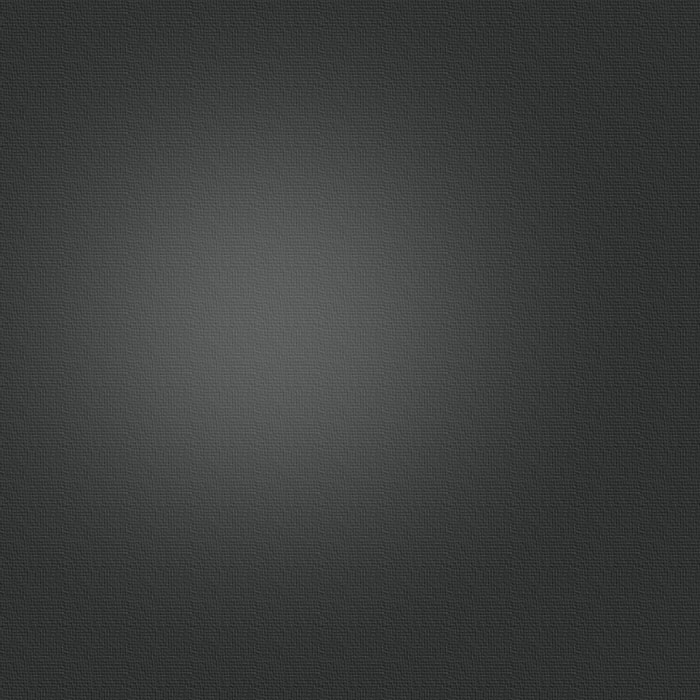
こうしてあぐらをかいて座っているのがさすがに後ろめたい。蒸し暑い夜中、真っ暗な茶の間にひっそりと、裸電球のスタンド一つだけ点けちゃぶ台を囲んでいる。既婚者の私が、深夜独身女性の家に、しかも両親と暮らす実家に勝手に上がり込んで夜食をとっている。くつろいだ振りをしていても、どこかでちぐはぐな思いが表面に現れてしまうだろう。両親とも二階で寝ているから平気、そう言われても気付かれなければいいという問題では無いように思う。
なかなか会う時間が取れなくて、結局こんな夜中に彼女の実家をたずねる事になってしまった。顔を見るだけでいい、いつもそう思いながら彼女のもとへと向かう。けれど、そんな表側の気持ちとは裏腹に、やはり恋人としての時間を二人で過ごしたい、そういった期待感を抱いて彼女との面会を求めていたはずだ。今日もそうだった。なのに私は茶の間にいる。彼女の両親が休む寝室の真下、一家の生活の中心の場である茶の間で、家長である父親の許しもなく、あぐらをかいている。私が握る茶碗も箸も、きっと父親の物だろう。彼に無断で私が借用していると思うと、自分のずうずうしさに嫌気がさしてくる。大切な一人娘に何の将来の保証も与えず、ただ恋人としてだけ求めてくる男に、勝手に上がり込まれ、おまけに自分の食器まで使われていると知ったなら、どんな父親でもそれを許すことはできないだろう。
私の思いをよそに、ちゃぶ台を挟んで向かいに座る彼女はくつろいだ様子だ。先に家族と夕食を済ませていたらしく、私が食べるのを黙って見守っている。身体を少し斜めにして座る姿は、それだけでも幸せそうに見える。彼女の長い黒髪と照射角のもたらす影が混ざりはっきりとした顔は見えない。けれどもそんな素顔を私は好きになれないのだった。挑発的な赤い唇、瞳を強調する強い眉。そして出来れば露出された美しい脚。細い足首。鋭角と緩やかな曲線の入交じった、香料の香るからだ。作られた女としての記号。それらを通してしか彼女を感じたくない。そんな本心を私は隠している。何を求めているのか本当は自分でよく分かっている。少なくても、畳み敷きの茶の間でのんびりと微睡んでいる事ではないのだ。疚しさを感じるのは、私が結婚しているからでも、また彼女の両親を気遣ってのことでもない。この身勝手な本音、見苦しい自分の欲望に対して疚しさを感じているというのが本当のところなのだ。
そんなはずないのだが、まるで蝋燭のようにふわりと、スタンドの明りがゆれた気がした。
明日からオカミの誘いで旅行に行く、会えばいつもする取り留めの無い話の中で、何気なくぽつりと彼女は言いだした。
二枚の航空券を手にして、ほら、と、もう準備が整っていることを私に示す。
オカミ。
彼女は最近付きあい始めた行き付けの居酒屋のおかみさんをそう呼ぶ。私は居酒屋へは行かないし、会ったことも無いのだが、オカミと聞くだけで何故か、髪を結い上げ、着物に割烹着姿の少し太った中年の婦人を想像してしまう。
オカミがお金持ちであることは彼女から聞かされていた。でも高価な航空券を彼女に買い与えるまで気に入られているとは思わなかった。二人の気が合う、という事以外関係の説明を求める理由もないし、ましてや二人の間に何か秘密があるだろうと詮索するのはどうかしている。だから怪訝に思いつつも、そのことはあまり表面にださないよう心掛けた。
ただそれでも目的地を聞かされたとき、さすがにおかしいと思った。初め聞き違いもあって、私がいつも混乱する二つの地名、一つは関東北部に位置する町、もう一つは神奈川県の内陸、山側の町名とまぜこぜになってはっきりしなかったが、いずれにせよ、飛行場、空港のあるような都市ではない。聞き返してはっきりすると、それはもっと大きな驚きに変わった。伊勢崎というのはそのどちらでもなく、横浜にある町だという。
そんなはずはない、と私は強く彼女を否定した。あんな都会の真ん中に、大型旅客機の離着陸が出来る場所などあるはずがない。そう主張すると、それでも彼女はある、という。ない、絶対にない。私が取り合わないでいると、どうしてそんな事が言えるんだと、逆に私をせめてくる。ならば尋ねるが、空港があったとして、どうして渋谷から東急線が出ていて二百円もあれば行けるというのに、わざわざ高い航空運賃を支払って飛行機に乗っていかなければならないのか。その質問をすれば、少しは省みてくれるかと思ったが、そうもいかなかった。彼女はますます主張を固め、むしろ私が無いと言いきることに対して強引さを感じる、とまで言いだすほどだった。その通りかもしれない。私が強く彼女を否定するのは、飛行場のあるなしではなく、最初の命題、オカミとの旅行、そのこと自体が自分の気に入らないからなのかもしれない。彼女は私の心の内を、直感的に見透かしているのだ。言葉の上の理屈ではなく、そこに漂う感情を彼女は捉えている。
ただ私にしてみれば、物事の理は理、感情は感情と分けて考えるべきであって、その発信源では混在していても、言葉として外に出した以上、やはり分離して判断するしかないと思っている。その点が彼女との衝突を生んでゆく。指し示すものはただただ指し示されるものであって、彼女のように、指し示すものが既にその掬い取れない影、凹凸をも含んでやっと成り立つ、とは考えない。いや、考えないのではなく、順序の問題、時間的な認識順序の違いだろう。私はいっきに全て捉えるのを諦め、まず切り取ってしまって、それから、どうしても汲み取れないなにかが浮き立ってくるのを見て初めて、やっとその事柄を理解してゆく。実は私の場合、そうしないと神経がまいってしまうのだ。それが狡い方法かどうかは別にして、あらゆる物事、事柄を誠実にトレースし、それをその場で心に取り込んでいくには、相当の負担が精神にかかる。いたずらに神経を摩耗させる危険がある。だから彼女の方法は私には不向きなのだ。
母親が降りてきた。もう口論に成りかかっていたから、気を付けてはいても、結構声を立てていたのかも知れない。襖が開いて寝間着のまま、彼女の母親が鴨居の下に立つ。私が茶の間にいることをどう思ったか分からないが、そう驚いた様子もなく、普通に、いらっしゃい、と挨拶してくれた。瞬間緊張した私もその一言で気持ちがほぐれ、崩していた脚を直すこともなく、自然に挨拶することができた。
取り立てて話すことがあるわけでもないだろうに、襖を開けたまま、彼女の母親はその場に座りこんだ。
こうして対面してみると、寝間着と普通の服との間に大きな違い、埋めようの無い隔たりをつくづく感じる。私も上はTシャツ、下は薄い布を縫い合わせただけの簡単なズボンという、大した格好ではないのだけれど、それでも寝間着にはならない。白と水色の細かい格子模様のパジャマはどこまで行っても寝間着で、普通の服を着た人と寝間着姿の人が同じ空間にいると、落ち着かない、場違いな印象ばかりが気になってくる。彼女の母親が、左目だけ瞑ったままいることに気付くのが遅れたのは、その為だった。
やろうと思っても出来ることではない。ぎゅっと瞼を閉じているのではなく、睡眠したままの、自然な、力の抜けた瞑り具合だからだ。けっして病的には見えてこない。ただ、そんな状態の人の顔を今まで見たことがなかったから、慣れないだけだ。
察したのかどうか、自分は、睡眠途中で目覚めると、いつも左目だけが眠ったままになってしまうのだと、開いたほうの右目をきょろきょろさせながら軽く説明してくれた。
夜中非常識な時間にやって来て上がり込み、しかも夕食の残り物を食らい込んでいる私を、さりげなく許す母親に安堵感をおぼえる。もちろん、父親がどう思うかは、全く別の話なのだが。
私は、おそらく彼女の母親が作ったであろう煮物の味付けを褒め、中断していた食事を続けた。
長居はかえって私を気遣わせると考えてか、頃合い良く部屋を出ようとする。
「じゃあ、明日からよろしくお願いします。」
去り際にそう言われたとき、一体何の事を言っているのか分からず、もう少しで聞き返しそうになった。
どうしたことか明日からの旅行は私と行く事になっている、そういうことか。
とっさに様々な思惑が脳裏を過った。
だが、ほんの少し反応が遅れただけで、いいえ、こちらこそ、という普通の挨拶がもう口を付いて出いた。
なぜ彼女が母親にそんな嘘をつかなければならないのか、実は最後までその理由が解らなかった。そして彼女もまた、嘘が発覚したにもかかわらず、悪びれた様子を見せないのだった。
夏の夜は短い。暗やみだと思っていた電灯のあたらぬ部屋の隅が、もう、ぼうっと見える明るさになっている。そんな明け方近く、玄関を開けるガラガラいう音とともに誰かが帰ってきた。そういえば、彼女の従兄弟が間借りしていることを、ずうっと前に聞かされた気がする。その従兄弟が帰ってきたのだ。
背広の片腕を残し、半身になって脱ぎながら、ついさっきまで猛烈に働いていた、というそぶりで茶の間に入ってくる。いやー疲れた、暑い、と言い、ふとそこに私がいたものだから、一瞬ひるむ。けれども、すぐ取り直し、ネクタイを緩めながら軽く会釈をするとそのまま、奥の部屋へと消えていった。
堅苦しい挨拶、紹介なぞされたらたまったものでもなかったろうが、かといって、あまりに何気なくこの六畳間を通過されるだけだと、それはそれで不安になるものだ。さっきの母親といい、この家に暮らす者は、予め知らされることなしにいる私を、一体どう思っているのだろうか。
食事を終え、それからしばらくの間、後片付けをする彼女が流し台から戻ってきたころだろうか。もうすっかり夜が明け辺りが明るくなると、従兄弟のいる奥の六畳間の方から不思議な声、お経のようなものが聞こえだしてきた。お経と言うにはあまりにも変化に富む旋律で、それでいて、太く静かに響き渡るその節はコーランに似ている。しかしそれでも、私の知るかぎり、今まで聞いたことの無い、名付けようの無い音楽だった。すると今度はそれがドローンのようになる、協和する二声の対旋律、あるいは主旋律とそれを強調する副旋律が、二階の両親の部屋から呼応するようゆっくりと響き始める。その、歌のようなものをどう説明したら良いだろうか。法華経でも、神道系のものでもない、日本というよりはむしろ、東南アジア、あるいはアラブ圏のどこかの古い儀礼音楽を思わせるのだった。いずれにせよ、使われている音律自体はめずらしいものではなかったが、一定の法則を思わせる構造、反復の在り方やこぶしのような細かい装飾音の付方、規則性が、民間伝承では無いことを物語っている。いったい何処の、何を目的にした音楽なのかは解らない。けれどあえて言えば、やはり宗教的な意味を含んだ歌唱音楽、カノンではないだろうか。
彼女の一家は、ある古い宗教を忠実に継承している、そして彼女もまたそんな環境で、その宗教観を自然に受け入れ育ってきた。そう解釈すれば、今までの理解に苦しむ彼女の言動全てが容易に説明できる。
その不思議な音楽がなっている間、一緒に歌いはしなかったものの、私のように特別なものと出会っているというそぶりもなく、当たり前な日常の風景として、彼女は気にも止めていないのだった。
私と行く事になっている伊勢崎への旅行。彼女が母親についた嘘を私は放っておいた。訳を尋ねず、そのままにしていた。だからだろうか。結局、私たちは本当に二人で伊勢崎へ旅立つ事になった。
ひんやりとした早朝の庭を真っ直ぐに横断してゆく廊下。玄関へ続くはけ道のような渡り廊下を彼女に先導される。
すると、奥の六畳間にいたはずの従兄弟がもう一度、上手側の玄関の方からやってくる。
彼女とすれ違い、そして次には私と鉢合わせになり、除けようもなくぶつかるかと思い、私ははっと目を瞑り身をすくめる。が、そのまま、彼は私を擦り抜けていった。
その従兄弟には実体が無かった。空気のように私と重なって通り過ぎてゆく彼は、まさに幽霊だった。
嫌な予感がした。彼が亡霊だろうが幽霊だろうが構わない。ただ、彼女が何かしでかすんじゃないか、どういうわけかそんな予感がした。
一瞬のうち、私が止める間もなく、彼女は向き直ると私に笑顔を見せ、そのまま私の脇を通過し彼を追った。私が振り返り彼女を見たときにはもう従兄弟に襲い掛かっていた。彼女は亡霊であるその従兄弟の首を後ろから両手で絞めていた。
悪い予感は的中してしまった。亡霊とはいえ、私の目の前で彼女は従兄弟を絞め殺してしまった。
多分初めから私には殺意を隠していたんだろう。最初彼が帰ってきたときは我慢できても、二度目に幽霊として現れた時には、もう隠しきれなくなったんだろう。秘めていた狂気が静かに露呈される。私はそんな現場に立ちあってしまったのだった。
幽霊を殺害してどうなるものでもなく、そのまま私は彼女を愛車に乗せた。車高の低い二人乗りのロータリースポーツ。古い国産車だが、夢の中では度々この車を運転している。
まだ茫然としている彼女を、ともかく助手席に押しやり、私は運転席につく。エンジンをかけ、強く引かれたサイドブレーキを下ろす。伊勢崎目指し、セカンドで発進した。
一九九六年七月二三日
1996年7月23日
カノン

