夏の終わりに
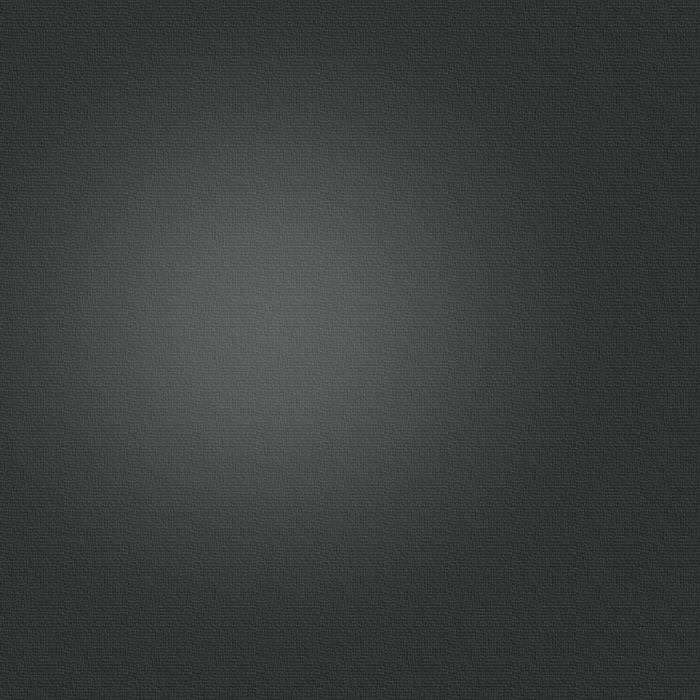
こないだまでの強い日差しは何処へ行ってしまったんだろう。薄曇りの空の下、草叢に虫が鳴く。耳を澄ますと小さな寂しい反復が野原全体を覆っている。八月の誕生日を過ぎてから、ようやく重い腰を上げて、この避暑地へやって来た。休みを楽しんだ人々が去った後の、今は閑散とした野原に一人立っている。
彼方に雑木林が見えるだけだ。避暑地と言ってもただの原っぱが延々広がる、つまらない場所だ。そこをぽつりぽつりと歩いている。
何を求めてここへ来たのか忘れてしまった。ただくすぶっていたくなかった。去って行く夏を見過ごしているのがいやだった。何処かに行かなくては夏が終わってしまう、そう思っていたのかもしれない。けれども暑い日は既に治まり、もう蝉の声を聞く事もなかった。
景色の変化を期待しているのに、どこまで行っても風景は変わらない。だらだらと傾斜地が続いている。
緩やかな丘陵をいくつか越えて行った。その道と出会ったのも、芝の丘を越えて下りにさしかかった時だった。上から見下ろす形で道に出くわした。草を刈りとっただけの未舗装道だが、道幅は広く、稜線に背く形で大きく左にRを描いている。昔そこを四輪駆動車で駆けぬけて行ったような気もする。でもそれが感違いであることに気付くのにさして時間はかからなかった。大きなコーナーの中心点にあたる場所に、骨組みだけになったサッカー用ゴールポストが置いてあるを見つけたからだ。道だと思っていたものは、実は使われなくなった競技場の一部、コーストラックだったのだ。
私が丘陵を下ってコーストラックへ近づいて行くと、まるでしめしあわせたように、左手のコーナーの付け根からこちらへ向かって美緒が歩いて来る。大きなスポーツバッグを肩に抱え黒の練習用スパッツを履いたまま、稽古を終えた美緒が歩いて来る。
彼女が舞台に立つようになってからもう随分時間が経つ。初めて会った頃はまだ舞台袖で手伝いをする学生だった。何の基礎も無く無口で不器用そうな美術学校の女生徒も、今ではカンパニーを代表するダンサーに成長し、自分の表現を見つけ、後輩の指導にあたるまでになった。そんな彼女も20代の後半にさしかかっている。
無愛想な少年のようだった美緒を知っているからだろうか。女性という意識で見つめた事はないし、さほど気が合うわけでもない。けれども、しばしば彼女と私はひょんな所で出会うのだ。それはまるで不安を持っている者同士が引き寄せられるように、とでも言えばいいか。
一緒に歩いて行くことにした。私の少し後ろを歩く美緒。特に話す事もなく、二人でコートを横切って行く。
カタカタ、カタカタ。
乾いた寂しい音がする。
さっきから彼女は缶ジュースを飲んでいる。それを時々、飲み口を指で塞ぎ縦に振ったりする。ビー玉でも入っているのだろうか、それがカタカタいうのだ。殺風景な野っぱらはその響きを殺してしまい、私の耳元で鳴っているかのように聞こえてくる。
その仕草が面白そうで、私もそんな音を発てながら野を歩いてみたいと思い、その珍しい缶ジュースが欲しくなった。
どこで売っているの?そう訊くと彼女は振り向いて遠くを指さし、過ぎてきた彼方にそのあまり見かけない缶飲料を売っている販売機があった事を教えてくれた。
私はもうそこまで戻る気はしない。立ち止まってその彼方を見つめはしたものの、曖昧に相づちを打つだけでまたのろのろと歩き始めるのだった。
私が諦めきれないでいるとでも思っていたのだろうか。彼女は下を向いて何か考えるような、思いだそうとしているような素振りで立ち止まる。
自信は無いけれど、と前置きする。その販売機はこの先ずっと行った所にもある、と言う。彼女の話では少なくても以前はあったらしい。その音の出る缶飲料を最初に見つけたのも、どうやらそこだったようだ。ただ最近そちらの方には行かなくなったし、その時分からあまりに閑散とした場所での不釣り合いな自動販売機に驚いたほどで、それで、今はもう販売機自体が無いかもしれない、と言うのだ。
どのみちこの野をつっきってゆくのだからそちらの方を通ればいい。仮にでも何か目的があれば疲れも少なくて済む。まだこの先、随分歩かなければならないだろうから。何を目印にするでもなく、私達は延々と続く草叢を歩いて行く。
美緒は中途半端に距離をあけ私の後をついて来る。決して並んで歩いたりしない。
途中、一軒の家があった。
その家はまだ建って日が浅いように思えるが、しっかりとした伝統的な作りの平屋だった。ただ、誰が通るとも知らない野原なのに、外塀も植えこみも無く、建物だけが簡単に、原の真ん中に投げ出されたかのようで、どこか居心地が悪そうに見える。そこからは賑やかな笑い声が聞こてくる。高い床で、しかも引き戸を全部取り外しているから、その家の縁側がある南側を歩けば、まるで能舞台でも観るように家の中が見渡せる。誰かの別荘のようだ。
聞き覚えのある声だった。といってもテレビに出ている時に比べれば少しゆっくりと低くしゃべっているのだが、襖を外した畳敷きの大広間で、真新しい柱に拠りかかっている甚平姿の男、それはキタノタケシだった。二三人の弟子に何か芸をさせて、自分はそれを見て楽しんでいる。彼にしてみれば珍しく休暇が取れたんじゃないだろうか。しかも時期外れの人のいない避暑地だから、芸能人であるがゆえ目立たぬようにする、という防備をすっかり忘れ羽根を伸ばしているに違いない。
そんな彼らの無防備さに、油断を突くように私達が水を注すのは考えものだ。大袈裟かもしれないが、私達がその縁側の前を通るだけでも、彼らの興を冷ましてしまう、と私は考えた。気付かない振りをしてこっそり通過するしかないだろう。
目を合わさないようにして通った。しかし彼らは私達に何も気をはらっていない。私の気の回し過ぎだったようだ。横目で見たキタノタケシは思っていたより小さな男だった。
人っ子一人いない野原を時折風が吹き抜ける。そんな時は、役目を終えた夏草が、カサカサカサと寂しい音を発てる。秋がすぐそこへやってきている。大好きな夏はもう終わっているのだろうか。
美緒の言う販売機まで来た頃には曇り空もほんの少しだけ明るくなっていた。その販売機はみすぼらしい家屋の玄関先にあった。
近ごろはあまり見掛けなくなった木造平屋、長屋形式の都営住宅が、一軒だけ切り取られ残されたような、小さな家だ。今は使われてないようだが、前の家主が自分で補修したのだろうか、あちこちに有り合わせの板切れが打ち付けられ、家が斑になっている。亀裂の入った曇り窓ガラスはセロテープで張り合わせてあり、その部分が黄色く変色している。そんな家が原っぱのぼうぼうと生い茂った雑草の中に埋もれるように建っている。そして自動販売機。うっすらと土埃を被り、傾いていた。
風雨に曝され錆が浮き出ている。それでも白地に赤、黄と、目立つようデザインされた販売機は周囲を無視して恥ずかしげもなく存在を誇示していた。そして、いたずらなのか事故なのか分からないが、見本を飾る展示ガラスが割れて、中の見本も幾つか無くなっている。退色してしまった派手な飲料メーカーのロゴが、がらくたとなってしまった今では滑稽にしか見えて来ない。
いつまで稼働していたんだろう。いくらなんでもこの箱にお金を入れてみようとは思わない。あまり期待していなかったけど、あのカタカタいう缶飲料を手に入れることは諦めなくてはならないようだ。美緒も私も、その見捨てられた家と朽ちた自販機の前で、しばらくぼうっとしていた。
ところがそれがどうしたことか、その家が留守中の伯母の家ということになっていて、次に私たちはその家の中にいるのだ。それも伯母というのが架空の伯母で、実在しない伯母の家に二人で上がり込んでいる。
西側に開いた窓が一つある茣蓙を敷いた四畳半。なんにもない、そのがらんとした貧しい家の中で、私たちは出掛けてしまった伯母の帰りを待っている。歩き疲れた私と姉は、向かい合わせに足を投げ出し、黙って壁に寄り掛かり腰をついている。そう、さっきまで美緒だったのに、知らぬ間に私の姉に代わっている。
買い物から戻ってきた伯母は今日私達がやって来るのを知っていたようだ。黙って台所の流しに立ち、駕籠から夕食の材料を取り出している。
やっと落ち着きこちらの部屋へくると、きちんと正座し、今度は取り込んだ洗濯物を折り畳みはじめた。姉も黙ってそれを手伝う。しばらくして伯母が初めて口を開いた。
「お父さんの具合はどう?」
洗濯物を仕分けしながら、架空の伯母は姉にそう尋ねると、もう伯母は小金井の祖母に変わっていた。
心配そうな祖母に、姉は手伝う手を止め、父の具合がかなり悪い事を告げる。もうだめかもしれない、そう言うと堪えていた涙をぽろぽろ流すのだった。結婚して今は別の場所に住む姉は、父と一緒に暮らしている私に、より詳しい父の具合を尋ねてくる。
父がどこか悪いだなんて、全然知らなかった。きっと母が私には知らさないで、姉と祖母には電話で伝えていたんだろう。ただそう言われれば思い当たる節もあり、春先に惹いた風邪を拗らしていたことが脳裏を過る。毎日の暮らしの中で父に接していると、かえって父の具合など見えてこないのかもしれない。
祖母と姉の三人で静かな午後を過ごすのは三十年ぶりだ。見窄らしい木造家屋は、昔の小金井の、慎ましやかな母の実家に重なってしまった。そしてこんなところで父の老を姉に聞かされて私は、いつかやってくると思っていた、遠い昔のことの不安を、離れたところから感じ入っているような、ぼうばくとした悲しみに陥っていた。野っぱらで美緒(姉)が発てていたあのカタカタいう音は、あったものが無くなってゆくときの、すき間ができるからこそ鳴る音だったのだ。
夏も終わり近くなってから、姉と二人、祖母の家へやってきたのだった。
一九九六年 八月二九日

1996年8月29日
夏の終わり
