早稲田通り
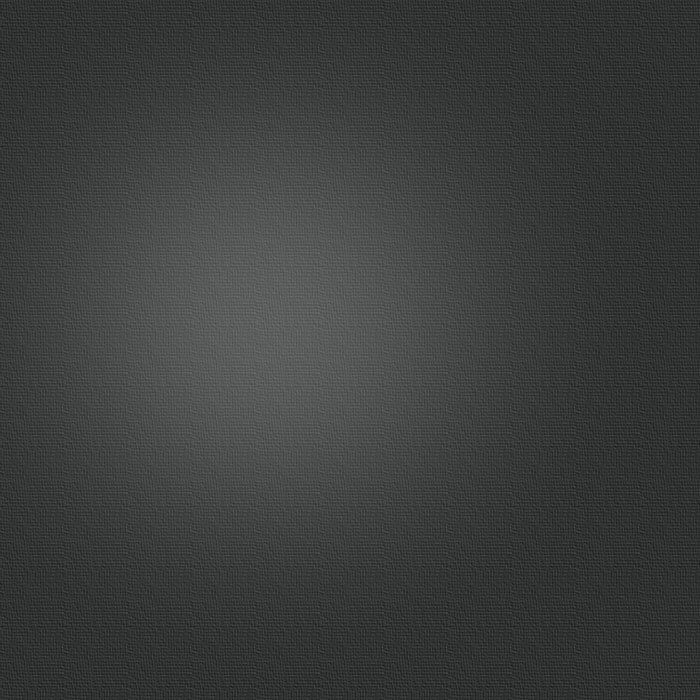
深夜の早稲田通りは、よく工事で渋滞する。
今夜もそんな渋滞にひっかかった。
歩道を狭くしているらしい。足止めをくった歩行者の長い行列ができている。終電ぎりぎりまでの会合が終わったばかりだから、二人の後ろにも他の仲間が並ぶかもしれない。あるいはもう、ひょっとすると前のほうに、先に出た誰かがいるのかもしれない。駅へ向かうには、どうしてもこの道を通って行かなくてはならないのだから。
いずれにしても、こんな状況では誰が何をしてるかなどわかりはしない。気にとめる人もいないだろう。だから、そういうときは、二人だけで個室にいるのと何ら変わらないはずだ。わずかな気を払うだけで、ちょっとした秘密の共有ができるということになる。
それで、もう、すぐ、そうなっていた。
点滅する注意灯。逆光で目晦ましされる工事用白熱ライトが見える。そんな所で私たちはそうなってしまったのだ。
ゆったりとした服。その下には暖かい身体がそのままであった。多少は人目を気にしているんだろう、だから後ろから。なるべく姿勢を変えないように。ゆっくりと。ゆっくりと柔かなところに触れている。わずかな、小さいもの。記憶の確認。確かにこうだった。私の知っているどれより、それは小さかった。わずかだった。確かに、今、この人に触れている証。感覚器官の倒置が行われている。触感が視覚に置き換えられていると感じ始めたとき、すでに『アシノツケネ』へと映像が移り変わっていた。そして、その場所を示す表現、言葉自体が、私にとってなつかしく、緩やかな響をともなっていた。
渋滞が続いている。列は少しも動かない。
自宅傍の遊歩道まで、歩きながらそんな事をしていたんだろうか。人通りのない深夜の住宅街だからといって、若い女性が何も身にまとっていないというのは都合が悪い。さっきもコートの男が、そこを通ったような気がする。どう思われるだろう。だいたいその人は、自分の持ち物を平気でそこら辺におきっぱなしにする癖がある。荷物と同様、服もその辺に脱ぎ捨ててきたにちがいない。路上にほっぽりだされたままの、リュックと上着の一部は見つけたけれど、そんなものではどうにもならない。はおるだけの、黒のゴム製チョッキでは、この肌寒い夜を一人で帰すわけにはいかないだろう。酔っ払いのように足腰の立たなくなったその人を支え、ともかく実家へ戻ろう、車の鍵をとってきて、送り帰そう、それがいい、そうしよう、と思った。
それにしてもこの人は若さの所為なのだろうか、後先のことをまったく考えないで生きてる。あきれもするが、同時にあこがれでもある。このあこがれに、私は強く引き付けられているのかもしれない。
遊歩道から実家の敷地に入るのは容易い。亡くなったはずの祖母がまだ起きているのだろうか、部屋に明りがついている。このはなれにそった細長い裏庭を通って行けば、誰にも気付かれずに私の仕事部屋へ入れる。彼女を先に、その狭い空洞を通す。大人が四つん這いになってやっと一人通れる、簡易式テーブル下の空洞。それはスタジオの、細長い折り畳み式テーブルだ。ミディコード、オーディオケーブル、電源コードの散乱する、わずかな通り路。
そこを彼女は器用に抜けていく。
膝を突いた、目の前の彼女のうしろを覚えている。
私は、いろいろと判っている所為か、例えば、この通路を確保しているテーブル脚が、触れただけでずれてしまうこと、とか、ケーブル類をなるたけ踏みたくない、とか、そんなことに煩わされ、思うように進まない。案内すべき私が、彼女より遅れている。裏庭(=折り畳み式テーブルの下)をやっとの思いで抜けたとき、もう彼女の姿は見えなかった。
実家の構造を知っている彼女は、きっと先に私の部屋へと向かったのだろう。幸運だったのは、この部屋に母が居なかったことだ。うっかりしていたが、裏の通路から来ると、どうしても母の寝室を経由しなければならなかったのだ。こんな夜中、なにも着ていないあの人と母が出会ってしまえば、いくらなんでも問題になる。母が用足にいっている間に、うまく通過してくれたのは幸いだ。
仕事部屋の扉を開けると、明かりを付けずに、ぽつんと部屋の真ん中にすわる彼女を見つけた。ちゃっかりと、どこにあったのかショールをはおり、こちらを背にして、椅子に腰掛けている。暗がりで振り向いたその顔が、にっこりと微笑んでいるのがわかる。私の、あらゆる心配を、この人は何とも思っていない。明るく、澄んでいる。
何か着るものをとってくる、そう伝え、私は二階の寝室へと階段を上がって行く。
いつものように、これくらいの時間、家内は深い眠りに落ちている。仮に「おかえり」と言われたところで、それは寝言のようなもの。意識からはほど遠い。
タンスの中を探す。なにか手頃な服はないだろうか。なるべく早くこの部屋から抜け出したい私は、結局、普段の部屋着であるセーターとズボンを選んだ。まだ返さずにいる赤いボタンシャツを選べなかったのは、持ち主を傷つけるような気がしたからだ。私には小さめなそのシャツは、去年の夏、突然ふりだした雨の夜借りたものだった。大きさが丁度良いので真っ先に思いついたのだけれど、あの人の肌に直に触れるのを想像すると、どうもつじつまが合わない、そうしてはいけない、という気になったのだ。
車の鍵を忘れそうになり、家内の枕元からそっと抜き出し、部屋を出る。すべてがうまくいっている。
階段を降りたところの廊下で母と出くわす。
着替えをもって仕事部屋へ戻ろうとする私は、そんなに不審でもないだろう。鍵のチャラチャラいう音さえ聴かれなければなんとも思われないはずだ。事実母は、なにも訝しがることもなく、これから犬の散歩へ行くところだという。
犬の散歩?
そんな時間なのだろうか。
遠いはずの朝が、こんなに早く来てしまうだろうか。この玄関とつながる廊下だってまだ暗いし、だいいち、鳥の鳴き声を聞いていないではないか。
扉を開けるシーンから先はさっきと同じだ。部屋の真ん中にすわる彼女、ショールをまとった後ろ姿、私に気付き振り返る。あかるい、くったくのない笑顔で。
ただ、さっきと比べて部屋が明るい。白み始めた外が窓越しにぼうとしている。
天気の悪い、鼠色の光りが、もう部屋を、彼女を浮き立たせていた。
いま丁度夜が終わるところだった。
一九九四年 三月十三日


1994年3月13日
