2001年3月4日
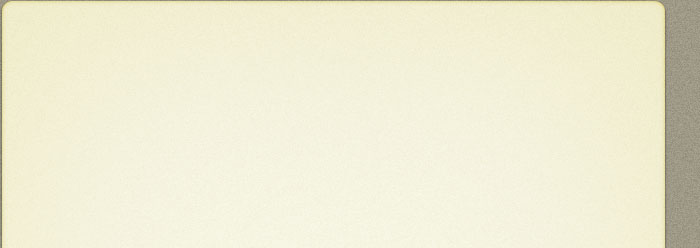
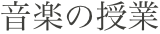
気をつけないと外へ転落してしまう。身体の左側を下に横向きで寝ている。
午後の傾いた日差しが、穏やかに家並を包みこんでいる。もう春だ。来年にはとり壊される木造建築の上階の、北に向かった窓から外の景色を眺めている。水色のペンキで厚ぼったく上塗りされた傷だらけの木製の窓枠。その幅が結構広いものだから、そこに身体を寝かせ、ぎしぎしいう教室を背にごろっと横になっている。
さっきからスズミさんがピアノを弾いている。ドビュッシーか、あるいは音数が少ないからウェーベルンだろうか、彼女はとつとつと弾いている。確か西側の壁に沿ってアップライトピアノが置かれているはずだ。だから彼女も私と同じように、他の学生には背をむけているに違いない。見てはなくとも、それを想像するだけでピアノに向かう後ろ姿が目に浮かんでしまう。きゃしゃな、ついこないだまで少女であった、ざんばら髪の後頭部を見ているような気がする。
音楽が、流れない。一音と次の一音が関係を結ばない。とどこおっている。それが美学に基づく表現なのか、それともそうとしか弾けないのか、解らない。
リピート記号に従い最初の小節に戻ったようだ。
その辺りから私もその曲の楽譜を見ている。手書きの、しかも見覚えのある、狭い間隔で引かれた五線に小さめに書かれた音符。これは私の筆跡みたいだ。だからこれは、ドビュッシーでもウェーベルンでもなく、私の曲なのかもしれない。そんな不確かな思いが作用してしまったか、寝転んでいる幅広の窓枠が、今度はピアノの鍵盤ということになっている。鍵盤の向こう側、本来なら打弦機構、饗胴のあるべき場所は相変わらず窓、すなわち外の景色が広がっているのだけれど、確かにピアノに向かっている、いや、実は、その鍵盤の上に横向きになって、左肘を枕代わりに寝転んでいるという、奇妙な格好になっているのだった。
更に不可解な現象が続く。身体を横たえているはずなのに私の右手は鍵盤を押す。弾くのではなく、彼女の演奏をなぞるように鍵盤を押しこんでゆく。音の出ないように、注意深く。しかしどうしてもたまに発音されてしまう。ピアニッシモの、出損ないなかすかな音が、彼女の音の後纔かに遅延して同音協和する。調律の所為もあるけれど、そのユニゾンは倍音に歪みをもたらし、音律上では矛盾する響きを生み出してくれる。
終盤にさしかかる直前の、ある重要な局面を向かえ彼女は静止してしまう。スズミさんにあわせて私は、もうその音を出す白鍵の上に指を置いている。その小節の最初の音、低音部記号の第三間に記された全音符、そこがいつでも弾けるよう準備している。けれど彼女は進まない。止まっている。音楽が止まっているのだ。
私の背後では緊迫した空気が徐々に広がっている。静止、音楽上の空白。そこには力が溜まる。時間の経過が、流れようとする音楽の、その行き場のないエネルギーをどんどん圧縮する。一体どうするつもりなのだろうか。ここまで増大したエネルギーをどう処分させるつもりか、勝算はあるのだろうか。段々私が、熱く、緊張してきた。この空気の重さを解消させる責任が、私にはあると思いこんでいるからだ。
時を見計らっていた。このいたずらに大きな休止を音楽的秩序、意味にいっきに転換させる最適な時、その定点を捜していた。まだだ、まだ。あせってはいけない。そしてもう、ここを逃せば瓦解する、と思う場所に近づきながら、なんと私は同時にうとうとしているのだ。
ふと意識がとぎれたかもしれない。瞬間眠ったのかどうか、判断できない。さっきの続きと今という意識に連続性があるのかどうか、確信が持てない。もしかすれば睡眠という空白を挟んだ可能性もあるはずだ。なのに私は音楽的時間感覚という、ただですらあいまいな機能に依存している。うつらうつらと緊張しているのだ。
ぽかぽかと暖かい。そしてとろっと、目をつむる、と同時にふわと浮くように戻される。眠ってはいない。まださっきの続きの中を経過している、ちゃんと、解っている。それでも眠い、眠い。何も起こらない事が気持ちいい。この気持ち良さの中で意識が遠退く瞬間がある。でも集注しなければ、時の流れを見失ってしまう、と思いつつうとうとする。
けれど思い切り、平手が鍵盤を叩いた。
平均率独特のクラスター・トーンが鳴り響く。
ここ、ここだろう。ここでなければ、もう音楽が成り立たなくなるというところで、中音部の、隣接する複数の鍵盤を平手で一まとめにして叩いた。今までにない初めてのフォルテシモを居眠りしながら叩いた。
これは滑っていないか。
空しく音が出ているだけではないか。
スズミさんのピアノが静止してから今まで、もし居眠りしていれば、経過秩序から外れてしまっているのだから。
しかし私にとってはここが音楽的意味のある場所なのである。眠る、という時間は、その主体から見れば勘定に入らない時間だから、やむを得ないのである。
いや、これは良しとしよう。
問題は二発目にあった。先ほどより少し上の(右の)鍵盤郡を、まとめて、中途半端な強さで弾いてしまった。
これがいけなかった。
頼まれもしないのに勝手に演奏に参加しておいて、挙げ句の果てに音楽を壊してしまったのだ。
恐くて後ろを振り向けないでいる。スズミさんも、この教室にいる人達も、困惑してるに違いない。この状況について誰か、言葉をもってあがなってゆかなければ解決できない、終われない状態にはまってしまった。多分もう、音楽は瓦解している。
あのとつとつと表現された前半部も、大きな空白として存在していた終盤部手前も、ただの事件、事象として「出来事」というカッコでくくられてしまうのである。もしここに鐘があるなら、誰か一発鳴らして欲しい。そうすれば、せめて終わる事ができる。終わりさえすれば言葉で締めくくることだって可能なのだ。
逃げ出したいからもういっそ、ぐっすり眠ってしまおうかとも考えた。
そんな時だった。突然スイッチを入れたように、途中から、外の、宣伝車の拡声器が鳴りはじめる。水前寺清子だ。うららかな春の日差しに包まれた住宅街を演歌が流れる。
昭和歌謡の特徴である、主音とその四度下を交互に動かす底音部に、内声を軽くする為に刻まれる短三和音。ミュート・トロンボーンとサックスのユニゾンが、水前寺清子の癖のあるポルタメントを強調する。
ブン・チャチャチャッ・チャ ブンチャ・ブンチャ、ブン・チャチャチャッ・チャ ブンチャ・ブンチャ。
風に運ばれ、音が揺れる。なんというのどかさ。あの空白に必要だったのは、こんな音響だ。
これでやっと均衡がとれた。さっきまで溜まっていた重苦しい力が、今開放されて行く。音楽が、解決されたのだ。
今演奏を終え、スズミさんと向かい合っている。木造校舎というより、山小屋をまねた古風な喫茶店のようだ。その薄暗いテーブルを挟んで彼女が座る。さて、私には負い目があるのだ。私の演奏は彼女の意に沿わなかったのではないだろうか。静かに、優しく微笑んでいる彼女に、そのまったく対局の、私に対する嫌気とかが隠されていないか、不安なのである。現に若いはずのスズミさんが、目の前で妙に老けこんで見える。私と同年代の、中学生くらいの子供を持つ女のように見えてくる。透き通った水々しい肌のはずなのに、喫茶店のランプを模した淡い明かりの所為でなく、確かに彼女の左目の下は荒れている。私を見つめる向かって右側の眼の下に痘痕がある。やつれさせたのは私に原因があるのだろう。
いたたまれなくなって他の学生に感想を聞く事にした。右側に身体を向けると、がらんとした教室の真ん中に、3、4人の学生が机に着いている。
彼等も何と言っていいのか悩んでいる様子だ。困ったような表情で顔を見合わせている。しばらくの間の後、その内の一人、男子学生が「わからなかった」と元気に言った。それはすごく正直な意見なのだろう。「良さ」もわからなかったし、音楽かどうかもわからなかった、という事なのだろう。
わからない、という言葉が今度は授業を中断させている。中断した流れを押し進めるだけの説得力ある言葉を、今私は持ち得ていない。止まったままどうする事も出来ずにいる。静まり返った教室の中、唐突に一人の学生が歯切れ良く話し始めた。アラシ君だ。去年卒業した彼は聴講生としてたまに参加する。今日もおそらく途中から授業に参加していたんだろう。気付かなかったが隅の方にいたらしい。その彼が興奮して話すのだが、どうやら先ほどのスズミさんとの演奏を絶賛しているようなのだ。そのような音楽がどうすれば生み出せるのか、しきりに訊いてくる。全て耳から世界を感じるのだよ、と説明するのだが、彼は私の話しなどちっとも聴いてない。ただひたすらしゃべりまくっている。
しかしそれでも、自分のした演奏行為を誉めてくれる人がいるのだから、それはそれで安心できる。はたして真実は解らない。本当にそれが素晴らしい音楽であったかどうか、定かではない。でも誰かがいい、と言ってくれればその場は収まる。それでいい。
ほっとした気分に戻り、あらためてこの部屋を見渡してみる。
床の間がある。
もうそこは、遠い昔に行った温泉旅館の一室だった。床の間に生けられた小さな蕾を付けた梅の小枝が、傾いた日差しの所為で長い影を作っている。
この上手からもう一度振り向き下手へ向くと、開け放たれた襖から畳敷の広間がある。そしてそこに学生達がいるのだが、その最前列、この部屋の敷居、鴨居のすぐ向こうに四人の制服姿の警官が並んで正座している。もちろん四人とも警帽は被っていないのだが、制服を着て折り目正しく正座している様は、どこか異様な光景で、今まで気付かなかったのが不思議なのである。
左から男、女、女、そしてまた男、と並んでいる。その左から二番目の婦警は、何とマキナなのだ。
マキナ。彼女が神戸で警察学校へ通いはじめたとは、噂で聴いていた。しかしこんなに早く警官になり、そして仲間を連れ、わざわざ私の授業に参加しに来たのには驚かされる。いったいどうして、今日、ここで、私の授業がある事を知ったのだろうか。また神戸から遠く離れた場所に、仲間とやってきた真意とは何なのだろう。
しかしこうして彼女と向かい合っていると、段々と周りの状況が見えなくなってくる。ここに彼女がいる理由を問うより、ここで出会えている事の喜びの方が大きいのだ。会いたいと願うと叶わず、無意識でいる時こそ彼女はやってくる。遠くにいるのではなく、実はすぐそこに、いつも一緒に生きているのかもしれない。
そこで私は彼女を抱擁している。遠ざかっていた暖かいものが、またゆっくりとやってくるのを感じる。
授業をそっちのけでいいのだろうか。
学生の目の前でこんな事をしていていいのだろうか。
そういう余分な想いも現れるのだけれど、やはり彼女を抱きしめているのだった。
2001 3/4

