家の夢
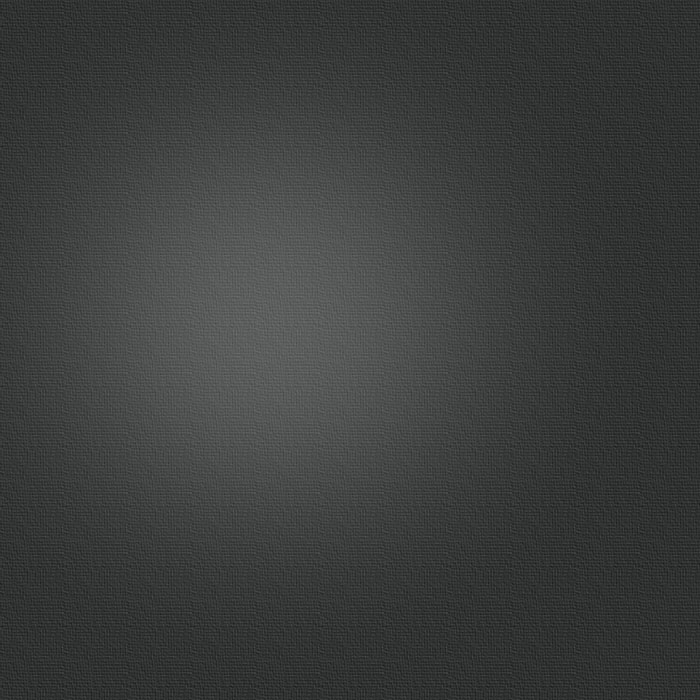
そこは母が納戸と呼んでいる部屋だった。
日の当たらない、家の北東部にある湿った奥の四畳半のことだ。
そこにベットが一つ置いてあり、私の寝室ということになっている。真夜中、マコトとヨンコがやってきて、今晩は泊まっていくと言うのだ。
築45年の家は、当時標準だった昭和の民家そのものである。壁や扉のある独立した部屋はない。襖によって仕切られているに過ぎない。マコトやヨンコがどうやってこの奥の部屋に入ることができたのか。玄関を上がって洋間を通り、母が寝ている茶の間を抜けないとこの奥の四畳半には入れない。暗闇の中、家人に気付かれないよう物音を発てずに忍び入るよう入ってきたのだろうか。もしかすると母はいないのかもしれない。まだ帰ってきていない。だから隣の茶の間には誰も寝ていないと解釈するべきかもしれない。
「シャワーを浴びてきます。」
マコトは我が家を知り尽くしているようで、さっさと奥の部屋を出て行ってしまった。
真っ暗な四畳半にヨンコと私だけが残される。灯りを点けていなかったのだ。
ヨンコはベッドに腰掛けている。
私はベッドの脇、茶の間側の鴨居に近い所にただ、立っている。
二人だけになるとヨンコの態度が変わってしまった。意外なことに、彼女は誘ってくるのである。驚いて立ち尽くす私の前で、ヨンコがもぞもぞと動いている。暗くてよく見えないが、ベッドの上で服を脱いでいるようなのだ。そしてそれは妖しい姿態を曝しているに違いないのだった。
ヨンコの豹変。それまで彼女に抱いていたイメージ、性的印象を一切呼び寄せないヨンコという印象が、目の前で崩れていくのである。
私は立ったままだ。微動だにせず、立ち尽くしている。暗闇の中で蠢くヨンコを見届けているにすぎない。
ヨンコの影が近付いてきたと思うと、私の右腕が彼女に引き寄せられている。右手の小指が選ばれたようだ。包まれ、吸引されている。それは臨海学校の記憶だ。富津の浜辺、磯巾着の記憶である。腔腸へ指を差し入れた、あの記憶なのである。
「ちょっと待って。」
ようやく口火を切って、ここが実家である、家族の暮らす家であることを彼女に話し始めた。
「今はいないようだけど、隣の部屋にはいつも母が寝ているんだし。」
そう言いながら説明するつもりで茶の間の方へ振り返ると、ぼうと目の前に人影がある。
いつからそこにいたのか、それはカナエサンだった。
滑稽な言い訳などする気にもならず、ただヨンコをカナエサンに紹介している。
しかしこの紹介という行為自体が滑稽なのだと気付いてしまう。ズボンを下ろしたままだったのだ。
結局みんなを泊めることになった。
そこで、各部屋の割り当て、布団の準備など、家族総動員で行っているのである。
まず姉が制作のヤツマヤ嬢を案内している。パパ・タラフマラ制作のヤツマヤである。彼女は寝ぼけた半開きの目で、とうに結婚して家を出たはずの姉に導かれて、母屋に付け足されたスタジオを兼ねた洋間へと向かっている。ここはまだ新しい。90年代に改築した部分なのだ。私は布団を抱えている。母から来客用布団のありかを訊いて、ヤツマヤのために布団を運んでいるのだ。
狭いと思っていたこのスタジオ兼洋間が、実は案外奥に広がっていた。応接セットが調っているし、このソファーをヨンコに振り分けても良かったんだと思う。最初からこの部屋に皆を通せば良かったと後悔している。
始終味を感じていた。それは、どろっとした血の固まりかもしれない。鼻血が収まった頃の、咽の奥上に留まったゼリー状の血の固まり。その鉄分を帯びた味が、始終感じられていた。
2008 8/28

2008年8月28日
家の夢
