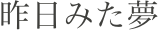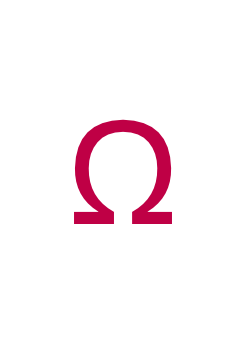年末から風邪を惹いたまま年を越す。おそらく微熱あり。
初夢にあたる昨日の夢、記しがたい表象的夢についてが、夢に出る。
今度はそれが三種類の図表となり、一つづつ検証してゆく。三つはそれぞれ三様の音楽にもなっている。しかし音の聞こえた節はない。
まず一月二日の初夢を一言で表現するなら『輪を懸ける紐』であった。
指、ではないのだが、指のような、指をもっと拡大したような、謂わば有機的円柱が一本、まず立っていたのである。その円柱の表皮内側に沿って一本の線、紐らしきものが輪を懸ける。表皮、薄皮一枚残してその内側円周に輪を懸けるのだから、それは透視されていることになる。しかも輪の懸け方が言葉では表し辛い。交差させない。括らないのである。オーム記号に似ているとでも云えばいいのか。しかしオームにしては線は紐のようであり、決して「戻し」が鋭角にはなってこない。緩くアールを描いた一筆書き、子供の頃漫画で見た正月の焼き餅、火鉢の上で丸くぷっくら膨らんで、タコの頭みたいになっちゃったというネタ、その輪郭線だけ抜き出したかのような輪の通し方。
もちろんそれは上から見た場合の話。夢の中では横から、三次元的に、多少斜め上の横からその輪を見つめてる。
問題は紐の両端だ。両端がそれぞれ上向きに反ったものと下へ垂れたものの二種類がある。いや、二種類とするのは誤りだろう。別に円柱が二本立っているわけではないのだから。状態の違い、時間的差異なのだと解釈すべきである。その時間的、状態的違いの二つの紐の両端が残像現象のよう二つ重なって可視化される。上向きのものと下下がりのものが重なって相殺され水平線になる、と、その時、スーッと穏やかになるナニカがある。「納得する」と言い換えていいもの、晴れてくるカンジがする。
『皮をむかずに中だけ輪切りにする方法は?』
そんなことしてまでバナナ食う必用あんのかなと子供ながらに思ったものである。小学生向けの『頭の良くなる本(の類)』に載っていた問題と記憶する。針と糸を用意するのである。答えは図解説明されていた。しかし針と糸でバナナの表皮をどう縢ったか、今では全く覚えていない。実際やってみたのだ。それは覚えている。図解通り針を通し、最後に糸を引き抜く時の、にゅるっとした手応えが悦楽を呼んだ。そうか、バナナでなくてはならない理由がここにあったか、と、そこに感心した思い出が蘇る。
『皮をむかずに中だけ輪切りにする方法は?』の糸の通し方。すっかり忘れているが、その糸の縢り方にきっと似ている、そう考えているのは目が覚めて、布団の中で、初夢をどう記せばいいか思案している覚醒したワタシなのである。やはり親が買い与えたか、オカも同じ本を持っていて、家へ遊びに行った時、部屋の隅の山積みの、がらくたに混じって投げ出されていた確かあの本に載っていたなと、小学校時代の友人を思い描いていた二日の朝。結局夢は記さずに、そのまま三日を迎える。
そのオーム字型の紐、線が、今度は三種類の図表に変換されている。小節線のような縦線で区切られた音価と音高を示しそうな記号が左から右へと流れてゆく。それを三回、見つめる。三種類のそういう図表があるようなのだ。それぞれ異なった音楽だと認識するが、だが音楽として聞こえた記憶はない。それより、ああ、これでやっと昨日の夢が説明できる、と安心している。
昨日の夢、紐の両端が「上向きのものと下下がりのものが重なって相殺される」のは均衡希求欲の顕れだ。
均衡希求欲。それは寝入り端や発熱時頻繁に登場する自動表象活動、幻妄に共通する因子なのだと思う。均衡希求欲が生み出す脳内映像の典型が今年の初夢だったわけだ。それに比べて今日の夢は均衡希求が働いていない。単に三つを検証してるに過ぎない。未来の、非投写型空中三次元電磁映像再現装置が、物質的には存在しない3Dモニター画像で目の前に青みがかった可視電磁波像を浮かべるように、透過フィルムみたいに波打って、音楽だと認知する図表で左から右へと流れてゆく。ただそれだけで、昨日の夢を翻訳可能にしてくれる、これでやっと「解った」のだと、そう感じさせているのである。まだ熱があるのだと思う。それで、もし均衡希求欲が働いているとするならば、対象は夢の中にあるのではなく、日をまたいだ、昨日みた夢が割り込んで、それと比較し均衡をとろうとしているのである。寝ながらにして、だ。
初夢についてこれでやっと説明できる、その安堵感が私を心地よい安定へと導いてくれる、そういう夢なのである。ところがどう説明できると云うのか、今となってはさっぱり解らない。
2011年1月3日