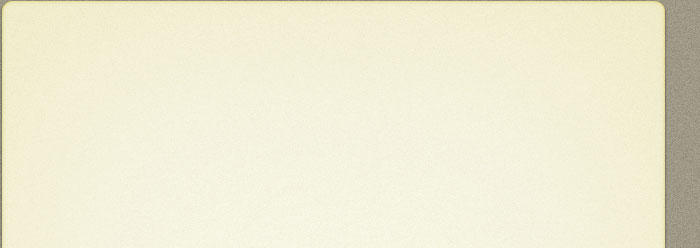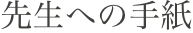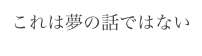此の間は座った場所がいけなかったと後から思うのです。横向の、左耳が教壇へ向いた位置。先生の声が左から直に届いてしまうんです。それで変な集中が起きてしまったのではないか、と勘ぐるのです。
というのは気の所為でしょう。思い込みの類と自覚してます。
それでも右と左、ここに自分は興味があるのだな、とそれをも自覚した次第。
日頃「イメージ」と言い表して済ませていることを正確にどう言っていいものやら未だに解決していませんが、脳裏に浮かぶ像、映像でしょうか。黒板に書かれたtourの図、聖ゲオルギウスの真っ二つ、そういう図も関係していると思われます。中心軸を持つ対称性が発火石になるような。
私は右と左を理解するのに手間取りました。幼児期の記憶です。どうも納得できなかった。どうして右と左が確定できるのか解らなかったわけです。母に言わせれば、要するに自分自身を定点・基準とする、ということらしい。もちろんこれは今の私の言葉ですが。いずれにせよ、自分を取り巻く空間上に絶対値としての「右・左」と名付けられた位置が存在するわけではないようなのです。幼児期、それが具体的に何歳だったか分かりません。しかし、それまで覚えた「ものの名前」とは決定的に異なっている。それが左右の概念獲得に手間取った理由なのでしょう。言い換えれば、自身を中心軸とする前提を意識していなかった、それまで自覚的でなかったわけです。
それともう一つ飲み込めないことがありました。母の説明は分かるとして、気儘な自分を中心にしていいものか、ということです。右方向だったものも、くるっと回れば逆になる、今度は左になっちゃうじゃない、という疑問。
「だからそういう時、向かって右、とか云うの!」と母を苛立たせたのでした。
どっちでもいいのに、どっちかを定めている不思議な言葉。基準にしている中心軸も、結局その「向き」により変動するとは困ったもの。目鼻口の向きだけならば、顔だけ捻ると大混乱「左右」は「前後」になってしまう。
「だから手。今手繋いでるでしょ?こっちが左。」
中央線のホームの上で手を引かれ、腕、体に付いたこの腕で右と左を決めるのだ、と取り敢えず覚えることにしたのです。
空間と云いますか、自身を取り巻く界隈、ワタシの立ち位置をぐるっと囲む360度、その空間上の何処か「大雑把な領域」を指し示す「右・左」という言葉の獲得。そこから意識的に空間を捉えることが可能となり、その後私は迷子になることもなく、デパートの館内放送『迷子のお知らせ』で名前を連呼されることも無かったわけです。
蛇足ですが時間について、未来を「前(前面)」過去を「後(後方)」と捉えた為、「5分前、5分後」の時点が逆転していた記憶もあります。その後時計の見方にも泣かされました。ようやく馴染んだ10進法がここで覆されたようで。でもこれはまた別の話...。
母とワタシの蜜月、次に家族の意識が芽生え、そして更に家の外、手を引かれて外に出る。外に出ると嫌でも空間を意識として捉えねばなりません。地図も方位も知らない時代、私の向いてる向きだけが方向把握の手立てとなる。ところがその私とは、絶えず変動してしまい、決して確かなものじゃない。自意識の成立に「右と左を覚えること」が一役買っているのは確かでしょう。自分を中心軸に置かねばならない。ところがその中心軸、向きは任意ときてるのです。今現在の私が発する分裂するような言い回し、これは自意識成立の段階でうっすら感じた不可解な気分のことなのです。
直立歩行になってから、ヒトの中心軸が口と肛門、性器を通る縦線となるのも暗示的。さらにその結果、嫌でも左右に優劣が生じてしまう、主体が分断されるのだ、と白日夢をみたわけです。
すっかり解った気になって、なんだそういうことなのかと納得したものの、やはりただの白日夢。実はちっとも解っていない。
気付けば右利きになっていた、と思っているのですがどうなのでしょう。どこかで矯正されたのでしょうか。利き手の存在も興味を惹かれます。脳の半球説からは利き手と言語は関係しているようです。従って人間以外の霊長類に利き手の偏りは無いとしている。言語、そして道具が介入しなければ、確かに利き手など起こりえないでしょう。
石器時代から左利きは少数との報告がありますが、それが北半球のことなのか、それとも南半球でもそうなのか、少し気になるところです。