豪徳寺
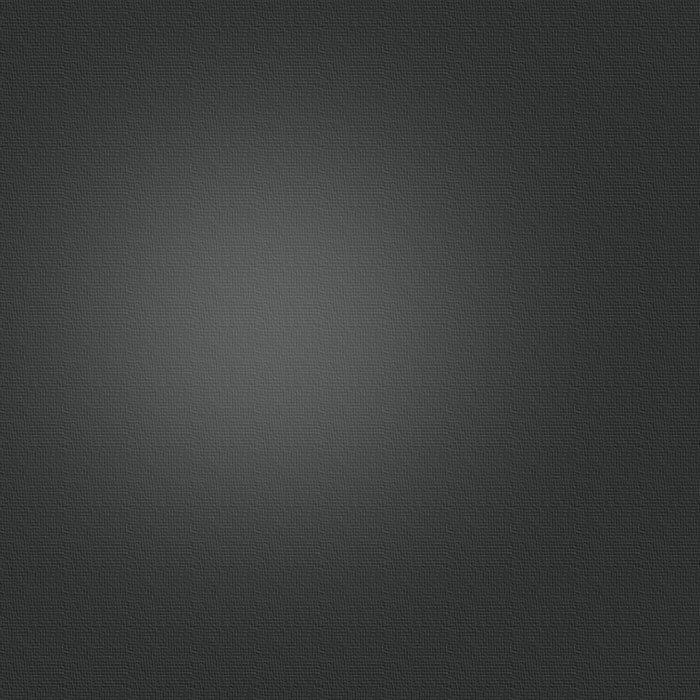
母がGTRを買ってきた。あの名車、スカイラインGTRである。早速夜道をドライブする。もちろん母を乗せて。
一般地方道だろうか。暗闇の中を真っ直ぐ、片側一車線の道が続く。街灯はなく、路面を照らしているのは前照灯の明かりだけだ。
運転をするうち視点の高さが気になり始めた。運転席をもっと下げるべきかもしれない。そうすれば手がハンドルに届く位置も今より改善されるのかもしれない。
そう、駐める場所を探し始めたのはシート・ポジションを調整するためだった。しかしなかなか適当な場所が見あたらない。ようやく駐車場付きレストランを見つけたものの、入り口は出庫する車が塞いでる。また適当な所があるだろうと走り続けたが、闇は途切れそうにない。諦めて路肩に停車しようとしても、今度は縁石が邪魔をして車を寄せられそうにない。
迷っているうちにずるずる走ってしまった。もう豪徳寺の町に近付いていたのだ。
ところでこの車、GTRは外装を持たない。ボディが無く、フレームにハンドルをはじめとする操作系と、あとは座席が付いているにすぎない。剥き出しの前輪、そのすぐ後ろ、左前輪側にはクラッチレバー、右前輪直後にはクラッチペダルが付いている。遊園地のゴーカートのようなものだ。そんなGTRの後部座席、正に吹き曝しの状態で母を乗せている。
こちらから来て丁字路で突き当たる。まだ町外れの、左折すれば駅前商店街へ繋がる寂れた交差点だ。信号機と共にそこだけが蛍光灯で照らされている。
赤信号で停まっている間、急いでサドルを下げてみる。そしてポジションを確認する。しかしどうもうまくいかない。クラッチとスイッチが紛らわしく、区別できずに慌てていた。信号は青に変わっていたはずだ。それでも停まったままでいられたのは、大型トレーラーが曲がりきれず交差点内で立ち往生していたからだ。駅の方から来て、こちらへ右折で入ってこようとしている。なんとか曲がりきったものの、今度は対向車線で停止してしまった。ドアが開いて運転手が降りてくる。走ってこちらへ向かってくる。何事かと思ったが、どうやら道に物が落ちてるらしい。運転手はそれを退けようとしているのだ。
結局シート・ポジションの調整が出来ぬまま、私は信号に従い左折する。駅の方へ、町の中心部へと向かっていった。
豪徳寺駅前は一方通行だらけ。しかも道幅が狭く、そこに放置自転車があるものだから余計GTRには抜けづらい。内輪差に気を遣いながら幾度か角を曲がる。路地が交差する度に顔を前へ突き出し左右を確認する。自分が何処へ向かうのか分からなくなっている。曲がるのは右だと感じても、標識の指示に従えば、そこは左折か直進しかできないのである。今曲がろうとしている角が、さっきも曲がったような気がしてきてうんざりする。もういい加減車を乗り捨てたくなってきた。
それでGTRを折り畳んで、駅裏の旅館に入ることにしたのだ。
表通りから引っ込んだ木造二階屋の見窄らしい連れ込み宿だった。常連なのだ。いつものよう庭から靴を脱いであがっていった。廊下を抜け誰もいない座敷部屋を通過する。灯りは点きっぱなし。襖も開いたままになっている。更に奥の四畳半へ進み、そこでGTRのシート・ポジションを調整することにした。明るく蛍光灯が照らす畳部屋で納得のいくまで調整してみる。
用は済ませた。こんな連れ込み宿でいつまでも母親といたくはない。誰とも顔を合わさない内に退散しなくてはならない。
あがってきた庭先へこっそり戻ろうとするのだが、どうも経路を間違えたらしい。うっかり先客のいる四畳半に足を踏み入れてしまう。ただ幸運な事に、その部屋には陰湿な空気が漂っていない。秘密めいた雰囲気が全く無いのである。結構な歳だと思うのだが、仕事帰りの禿げ茶瓶が胡座をかいてご機嫌でいるのである。一杯ひっかけてるらしく、顔が赤い。他に二三人いたと思うが、女連れというわけでも無さそうだった。適当に誤魔化し、私と母が座敷を横切っても、何か可笑しな話でもしてるのか座は盛り上がったままなのだ。
幾つか座敷部屋を通過して、なんとかあがってきた縁側、庭先の縁側にたどり着くことが出来た。ところが靴が見あたらない。踏み石の上に脱ぎそろえたはずなのに。
場所柄だろうか、この旅館は私のような使い方をする輩が多いようである。目の届かないのをいいことに、お金を払わず、小用だけ済ませさっさと抜け出してしまう。それを弁えた宿の従業員が履き物を表玄関に移してしまう。私と母の靴も、きっと持って行かれたのだ。
狭い廊下の突き当たり。暖簾の向こうが表玄関だ。申し訳程度の帳場がそこに設えてある。眼鏡をかけた三十代と思しき女性が帳場に着いている。化粧もせず、構わない服装でいる。家族で切り盛りしてるに違いない。奥から出てきた年端の行かぬ子供がまとわりついている。
どう言い訳するかは予め決めておいた。
「すみません、いつも使ってるんですが、今日は用事があったことを忘れて、うっかり入っちゃったんです。すみません、出てもいいですか。」
「ああ、いつもありがとうございます。はい、どうぞ、またいらして下さい。」
こう見えても、実は案外美人なのではないか。
彼女は笑顔で私と母を通してくれる。
表玄関と云っても、勝手口のような粗末さだ。ここは裏口で玄関は別にあると感じさせるほどだ。宿泊客の脱いだ靴が散らかっている。三和土は浅い。上がり口との境界、段差が低いのである。ごちゃごちゃと脱ぎ散らかした靴の上、今持ってきたばかりで一番上に揃ってきちんと置かれた二人分の靴。浮いたように見えるそれが私と母の靴だった。
おきれいですね、と母が声をかけられている。驚く、というよりまず心外だった。母に対してそのような形容がなされること自体異様だったし、年老いた母親を私の連れ、恋人と誤解されたことが「あり得ない」を通り越し、例えば、食べても意味のないものを食べてしまった時の「無味感」、吐くまでではないが、摂取すべきでないものが喉を通っていった後の「後味」、それでぼーっとしているというような。
全く感じたことのない感覚を、既に感じたことのある感覚に置き換えることなどできっこない。放心、身に添わない、という表現でもそこには届かない。不快ではない。しかし快いものでもない。
訝しいことに、今まで何度も母とこの宿を利用していたという憶えが無いわけでもなかったからである。母親とちょくちょく連れ込み宿に出入りしていた、そう思い始めているのである。
宿を出て駅裏の入り組んだ路地を歩き回っている。捜しているのである。宿に入るまで乗っていた、あのスカイラインGTRを捜しているのである。何処に駐めたのだろうか。全く見あたらない。場所を思い出せないだけでなく、駐車した記憶の抜けていること自体不可解だった。夢なんじゃないか、おかしい、と感じ始めていた。
「これ、何か咲いているのかな?」と母が訊く。ふと脇に目を遣るとアジサイのような植物が生えている。路地裏に建つ古い民家の板垣、その下半分、板の張られていない部分から庭のアジサイが溢れているのである。闇に暗く沈んだ葉の茂み、それは見えるのだが、花など咲いているだろうか。気になったので屈んでみた。すると下の方、葉っぱに紛れて何かついている。だがそれが花かどうかは分からない。花だとすると、去年の夏からずっとそこについたままになった乾いた花だ。それを「咲いている」と云えるだろうか。訊ねられても答えられない。アジサイかどうかも確かではないのに。しゃがんだまま、私は母の質問に答えられずにいた。
二〇〇九年 十二月十四日
N.Y Queens 40st.のアパートメントにて
2009年12月14日

