2009年8月1日
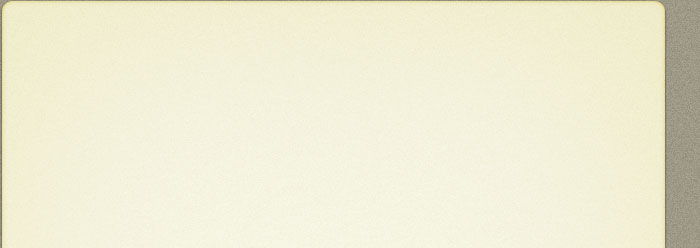


古く老朽化した劇場の舞台裏のような、黒々と艶出し材の染みこんだ板張りの床が全面に広がる木造の古めかしい建物の中。少なめの蛍光灯でどんより照らされる講堂は、広さから云って稽古場なのかもしれない。芝居の稽古場だ。そこを人がぞろぞろ歩いている。男女が一列円をつくりゆっくりと、まるで輪舞でもするよう歩いてる。学生、芸工大の学生たちの輪なのかもしれない。
そんな光景を母と二人、脇で突っ立って見ている。
どうも学生とも限らないようだった。列の先頭はオクヌキカオルさんだった。
なんて素敵な人だろう。綺麗な人だと心の内で思っている。と、一緒にいる母も同じ事を感じていたようだ。
「あの人は素敵だね。」
はっきりそう言う。
やはりそうでしょ、と私は思う。
オクヌキカオルさんに続いて歩く男性に目がとまる。私はその男性をよく知っている。だから思うのだが、彼は面白みのない男である。
何の魅力もない冴えない男。
母もそう感じたらしい。初めて見ただけで、彼の魅力の無さを見抜いていた。
母の感性、人を見る目に感心している。
二〇〇九年八月一日
関連
母親:船着き場
