世田谷図書館
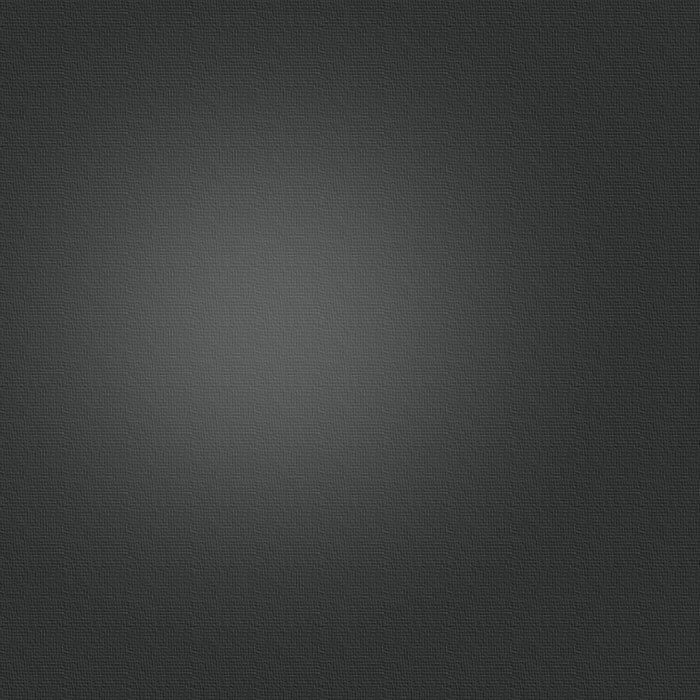
晴天。心地よい中秋の正午、山の手線環内を横断する是政線に一人で乗っていた。雑司ヶ谷、早稲田、はっきりとはしなくても、多分そんな辺りを走っているんじゃないか。のんびりと都内を横切る単線のこの電車は、いつでも降りられるよう、扉を開けたままでゆっくりと、コトコト走っている。
ひなたぼっこをするように、そんな開け放たれた乗車口の脇に立って、ゆられながら、通過する街の景色を楽しんでいた。それでも、少しだけ傾いた暖かい日差しがやはり眩しかったから、視線を落して線路の玉砂利ばかり見つめてた。
だから水路にはすぐ気付いた。線路に沿うように水路が引かれている。豊かに澄んだ水が、勢いよく流れている。都心では考えられない光景だ。不思議に思い、私はその開いたままの乗車口から身を乗りだし、線路伝いに続く水路の行方を追った。
都内の、しかも家のすぐ近くに、こんな街があったのを知らなかった。どうして今まで気が付かなかったのだろうか。水路は街のいたるところにある方形の浅い溜め池に水を運んでいた。
整然と区分けされたプール状の水溜めは、コンクリートでしつらえてあるものの、苔の生え具合からみて、かなり古い時代からのものだろう。川の浅瀬のような程よい深さの溜め池は、用水路からたえず流れ込む水で、淀むことを知らない。澄んでいる。まるで池の底から照明をあてたかのように、きらきらと揺らぐ光が立ち上ってくる。
水の街。私は都心にあるこの美しい街に、今日初めて出会った。
いくつかの建物は池の上に建造されていた。私が立ち寄った寺院も、池に支柱を下ろした、水上建築だった。
この寺院は観光名所になっているようで、薄暗い院内では、昔の、この地域一帯を支配した豪族の残した武具や漆器、文献などが展示されていた。光の取り込み具合。古い日本建築は、そのことを究めている。日射というものが扱いによっては有害な宇宙線になってしまうことを知っている。刺さるように直進してくる太陽光をどう屈折させるか。同時に、間接光と逆光を利用して、空間の重みを視神系に伝達させる工夫。構造だけではアナリーゼしきれない、知覚と感覚の統辞法。今私が見ているものは、三次元を物理的に構成した内部空間ではない。目に見えないもの。時間の集積を見つめている。
回廊を一通りめぐった後、正方形の大きな土間を囲んだ広間に出た。板張りの上をそおっと歩く観光客がぽつりぽつりといる。音を発てぬようにするから余計、ぎゅう、と鳴る軋み音が、心地よい間合を取って室内に響く。
秋の日差しが、この土間の中央に注がれている。薄暗い広間を直線的な傾斜光が横断し、そこだけに陽が当たっている。瞳孔が追い付かなくて、ただぼうっと白い光の柱が建っているかのように初めは見えた。目が慣れてくるとそれは、髪を短く刈り上げ、白い円錐型の無機質なデザインの衣装を着た、小柄な人が立っているのだった。
シシダ・イクコ。上半身がゆっくりと動いている。人前で演じるというのではなく、ただ展示された物のように、儀式的で、意味不明な仕草を繰り返していた。
実は今ごろ、劇場では仕込みをやっているはずだ。本公演がもうすぐ始まる。私は一足先に仕事を終え、こうしてぶらぶらしている。けれども役者はそんなゆとりも無いだろう。本番を控えて、練習、リハーサルに明け暮れていると思っていた。しかし、どうもそうでもないようで、シシダ以外の役者は、観光客に混じって院内を拝観しているようだ。こんな時だからこそ、誰もがこういう静かな場所にやってくるのかもしれない。私は今まで、近くにこんな所があるのを知らなかったけれど、ここは結構有名な、都内の名所なのかもしれない。もう永いこと東京で暮らしているけれど、水の街を知らなかったのは私だけだったようだ。
水の街を後にして、私は再び是政線に乗り、世田谷を目指した。図書館に用事があるのだけれど、そこへの交通手段は、この是政線一本しかない。
わざわざ遠くからも人がやってくる世田谷図書館は、確かに珍しいレコードが手にはいる。この図書館の魅力は、CDの品揃えの多さ、充実した音楽ライブラリーにある。私と同じようにCDを買うお金を節約する人にとってはうってつけの公共施設だ。
そんな図書館だから、フロアーは都心の大型レコード専門店と見間違うほどだ。新譜のディスプレイまである。違いといえば、人がまばらな事と、音楽が鳴っていない事なのだが、それが唯一、ここが公共施設であることを知らせている。情報は沢山ある。けれどもそれは隠されている。音はものの在りかを示す、表示灯でもあるのだから。
人目を引く派手な色彩の壁面やパネル、わざわざスポットをあてられたジャケット、ロゴ。レコード店ではロー、ハイをブーストした音がそれを際だたせ、私たちを興奮状態に陥れてしまうのに、ここは違う。見た目は同じでも音が無いから、空間が沈んでいる。色彩は曇っている。考えてみれば私たちは、都市でいつもウーハーの振動に揺らされている。音がなければ本当は、この図書館みたいに、沈んだ、静寂の喧騒という、ちぐはぐな世界に立ち入っているのだろう。
特別探しているCDがあるわけでもなく、ジャンル分けされた棚を一列ごとになんとなく見回していた。借りられる枚数には限りがある。どれも聞いてみたいが、あてがないから、絞り込もうとすればするほど、どれも同じなような、どうでもいい気分になってくる。
洋楽ロック系棚の最上段を探っているときだった。レジ、というのも矛盾してしまうのだけれど、もう店と取り違えているようで、その、棚越しのレジで、コバヤシが店員をしているのを見つけてしまった。
そんなことしていていいんだろうか。彼女も新人ながら役者だから、夕方からのリハーサルには出なければならないはずだ。さぼるつもりなのだろうか。従業員専用の薄緑の前掛けを着用し、店長風の男性の指示に従って、山積みになったCDをジャンルごとに分類している。仕事をこなす生き生きとした彼女の表情から察するに、私がここに来ていることには気付いていないようだ。確かにリハーサルまでにはまだ時間がある。もしかするとさぼろうというのではなく、わずかにあいた時間で生活費を稼ぐため、ここでアルバイトしているんじゃないだろうか。みなには内緒でこっそり働いているんじゃないだろうか。そう考えると、疑ったことが恥ずかしくなり、暇でぶらぶらしている自分が急に情けなくなってしまった。気付かれない方が都合がいいのは私だ。日がな一日是政線に乗ってのんびり過ごした自分を、彼女に見取られたくはない。
客の呼びかけに応じ、向かいのジャズコーナーに彼女が来たとき、私は思わずしゃがみこみ、棚の陰に隠れてしまった。
貸出カウンターでは、中年の女性が係員を務めている。そこへ持って行き、住所、氏名など、いくつかの項目を書類に明記してゆく。奥の整理棚から出てきた係の女性にその書類と借りるCDを差し出すと、そっけなく突き返されてしまった。書類が違う、という。なるほど、カウンターの上には別の、無漂白の用紙がある。ダンボールからのリサイクルだろう。薄茶色の再生紙が廃物利用なのか、菓子箱の中に束になって置いてある。もう一度その用紙に必要事項を記入し、よく確認した上で提出した。奥から仕事を中断し、機嫌悪そうに出てきたその中年女性は、また違う、といって、突き返してくる。すると、私だけでなく、そうやって突き返されている人が他にもいるではないか。いいかげん怪訝に思い、どういうシステムなのか問い詰めてみた。
彼女の説明によると、まず係員に声を掛け、カウンターの奥にある申込用紙を取ってもらい、それに記入してから初めて貸出手続きが完了するのだ、ということらしい。
おかしいではないか。それなら、最初に間違えた書類を提出した段階で、その正式な申込書を出してくれれば済むことではないか。だいいち、何種類もの紛らわしい記入用紙をカウンターの上に置いておきながら、肝心な申込用紙を奥にしまっているなんて、どう考えてもおかしい。公共施設だから多少の不便は我慢するが、いくらなんでも機能的ではない。ましてや、その係員の態度はひどすぎる。不親切きわまりない。何が偉くてそんなに威張っているのか。
私は興奮して怒鳴りちらしていた。私が怒鳴れば怒鳴るほど相手の中年女性が醒めた態度をとるので、余計腹立たしくなり、怒りだけが空回りしていた。
静閑とした図書館のロビーで、私の大声が響きわたっていた。だから目が覚てもまだ興奮していて、もしかすると本当に大声を出していたかもしれない。
一九九五年十一月二二日
1995年11月22日
世田谷図書館
